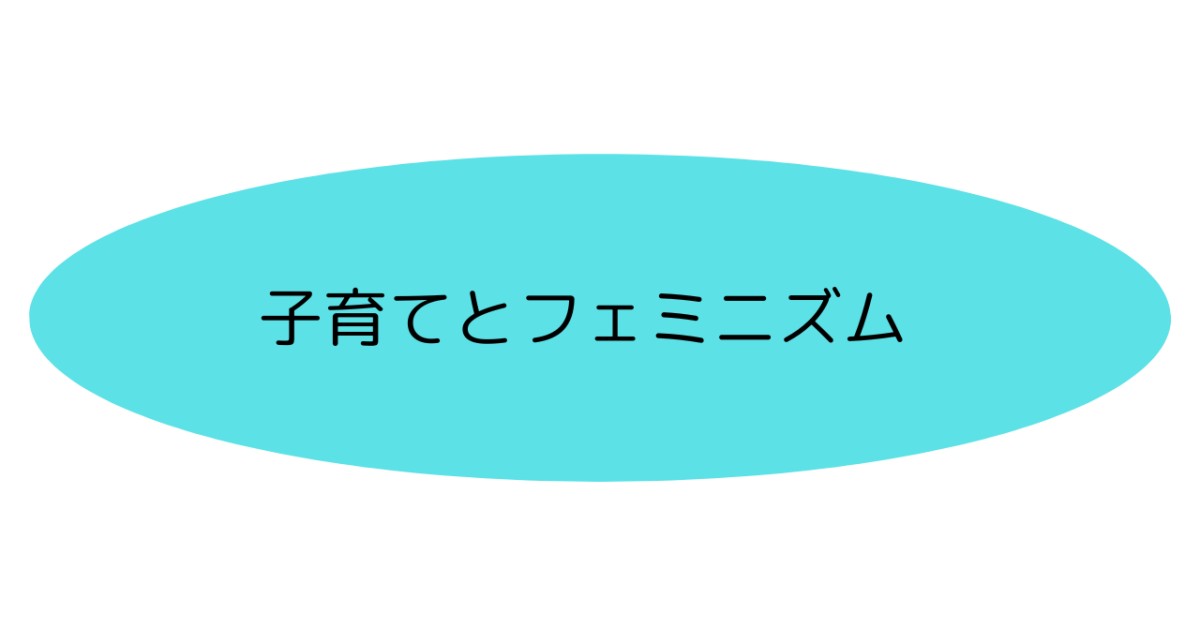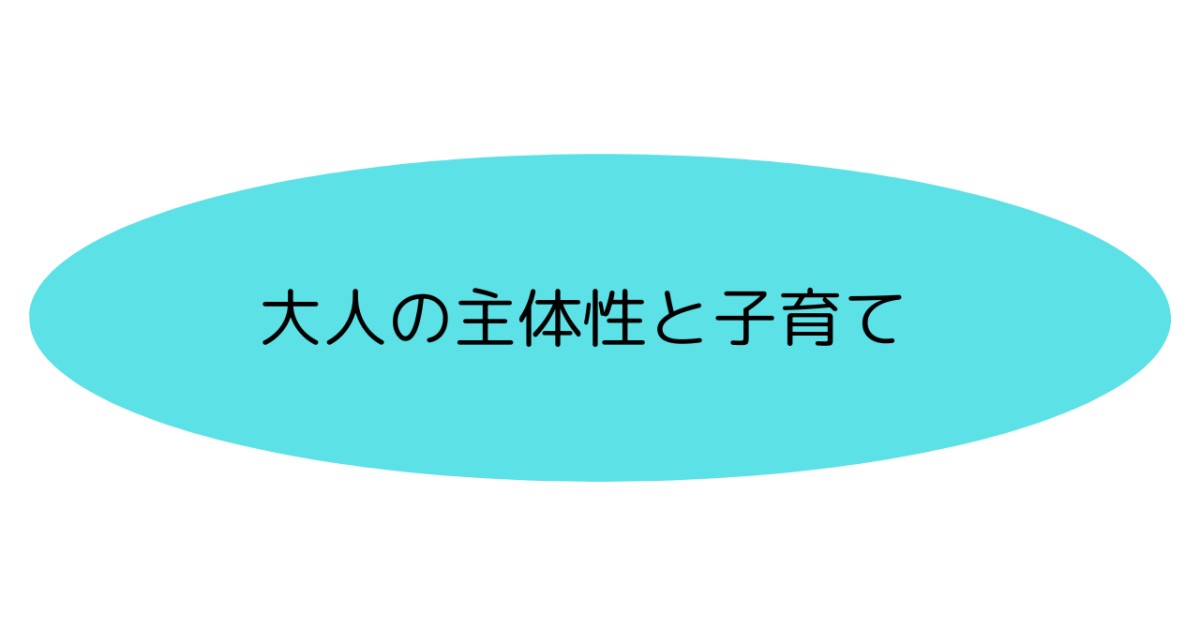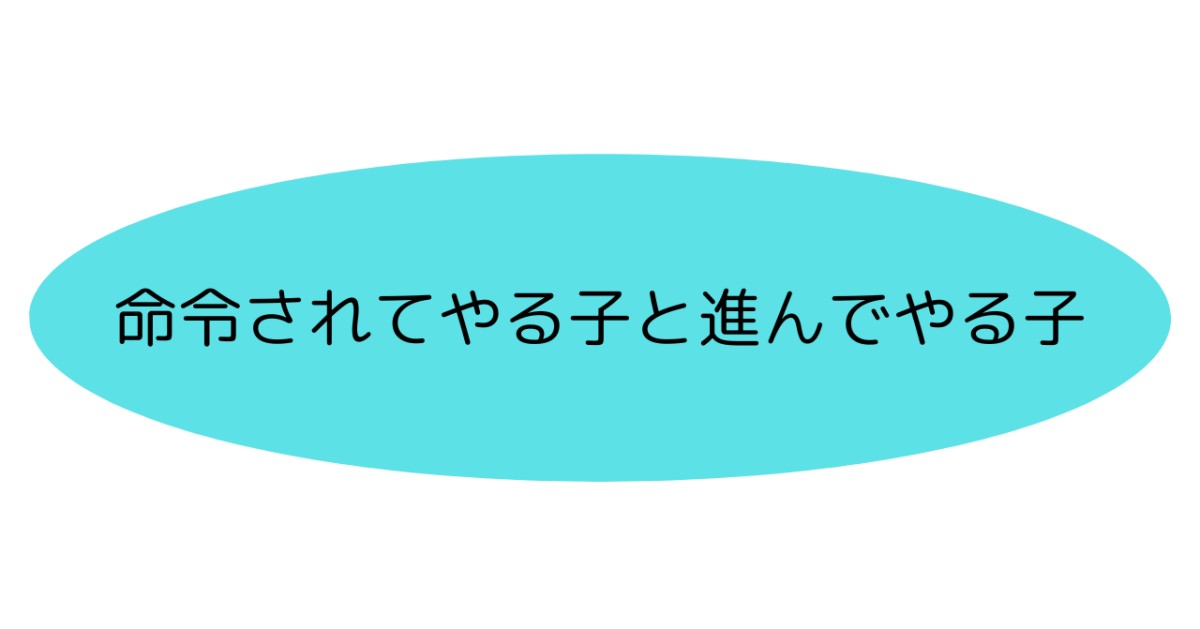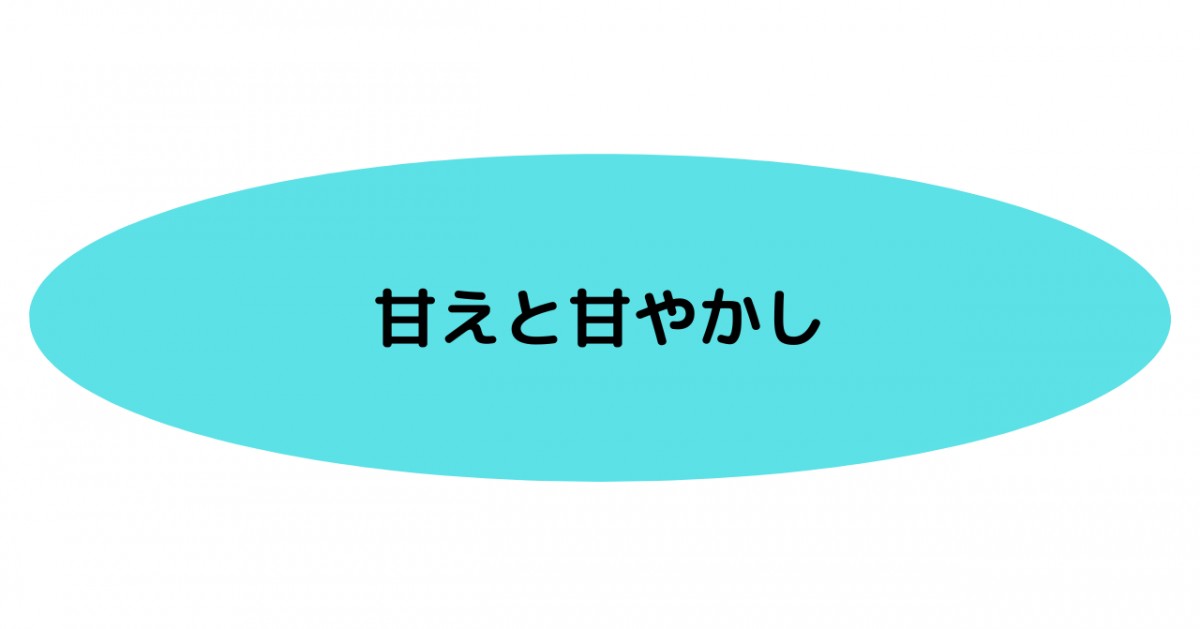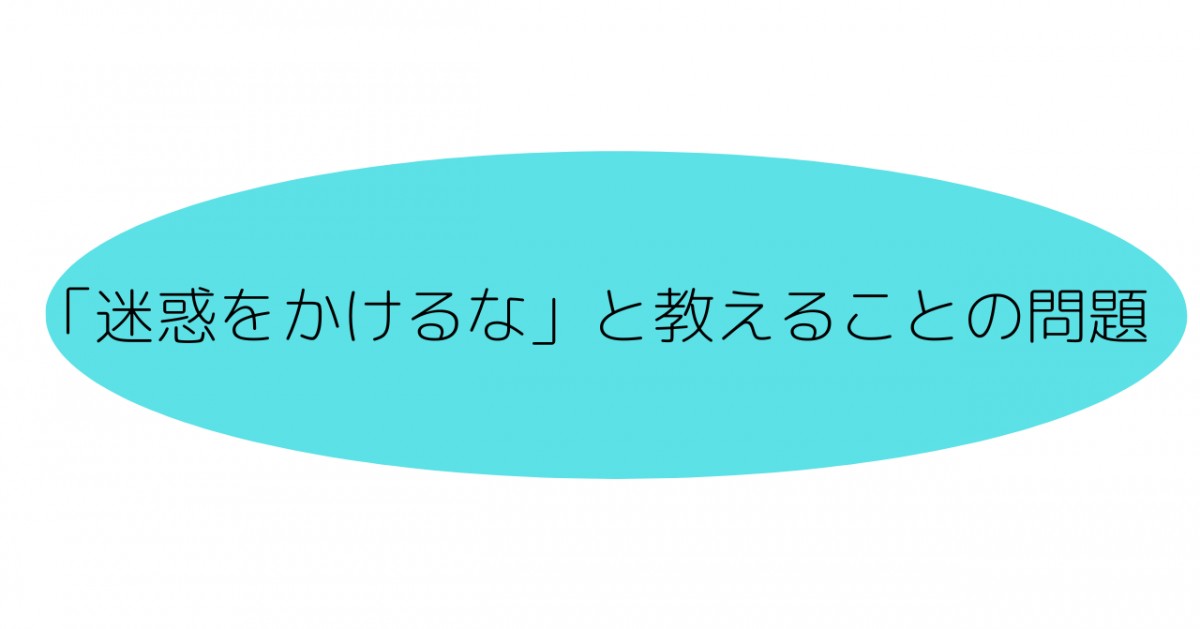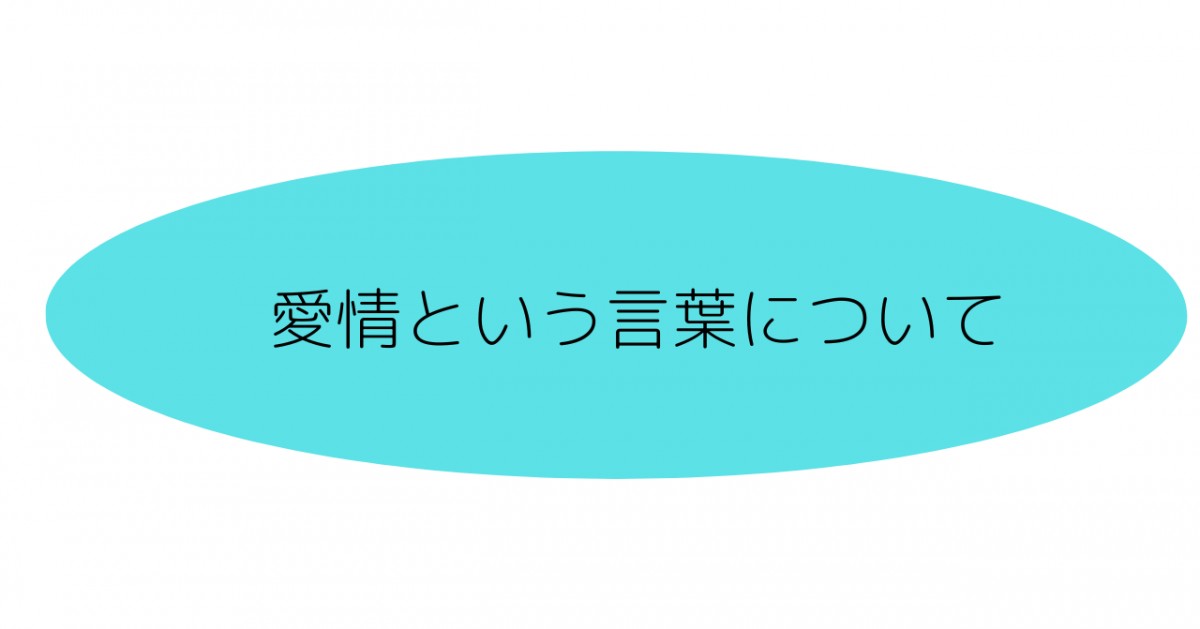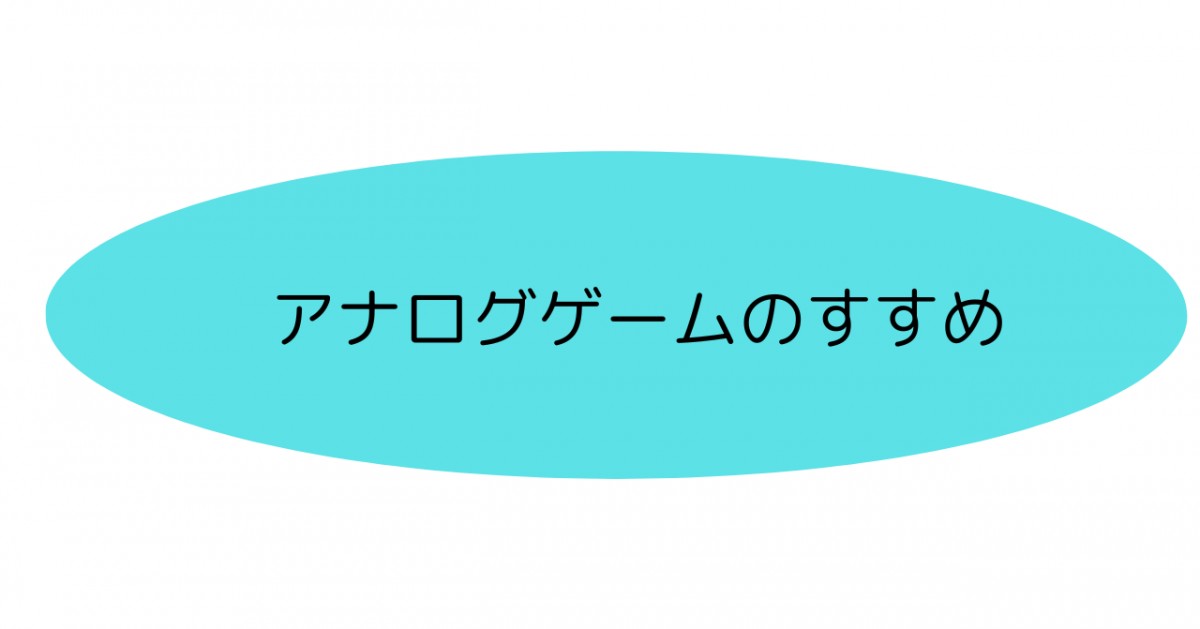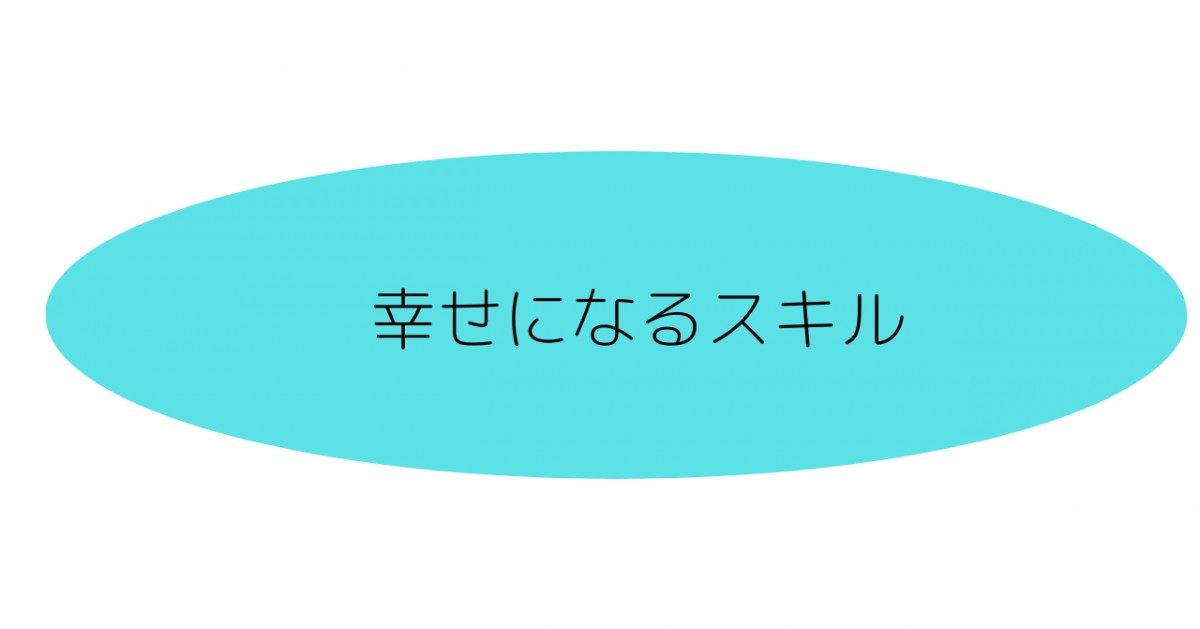泣きは言葉
子育ての最初の難関といっていいものが、おそらく多くの人にとって子供が泣くことではないでしょうか。
これをどうとらえ、どう関わっていくかで、その後の子育てのあり方や、人格形成に大きく影響することでしょう。
ですので、今回はこの子供の泣くことについて見ていきたいと思います。
たいていの人にとっては子供に泣かれると、ストレスを感じたり、不安になったり、イライラや怒りといった感情を刺激されることでしょう。
まれにとても楽観的だったり、元々の性格が明るかったりおおらかだったりして、泣かれても動じずに許容的に受けられる人もいますが、もはやそれはある種の才能と言っていいレベルのことですね。
子供の泣きに接してそれを負担に感じるのはごく自然なことだと思います。
自分自身が、子供の泣きでその子がイヤになってしまうことに罪悪感を感じて自分を責める人は少なくありません。しかし、それは少しも悪いことでありません。それはしごく普通のことです。
まず最初に伝えたいのはタイトルにも挙げたように「泣きは言葉」である点です。
子供はまだ言語のコミュニケーションが獲得されていなかったり言葉が話せるようになっていても自分の感じていることを言葉にだすことがまだ未発達だったり、ボキャブラリーが少なかったりします。
なので、泣きを通して伝えようとします。
なので、泣くことは元々少しも悪いことではないのです。
しかし、泣くこと自体をよろしくないことなのだという認識も一般的にあります。
なので、子供が泣くと慌ててしまって、すぐに泣き止ませなければと考える人も少なくないですね。
そこから実際に行われるのは、あやし→ごまかしの関わりが多いです。
泣き止んでもらうために、あやしたりごまかしたりすることが悪いというわけではないのですが、ここで考えて欲しいのは、最初からそうしなくてもいいということです。
この記事は無料で続きを読めます
- ◆「どうしたの?ああ、そうなんだ」
- ◆子供の多様性と大人の多様性
- ◆人格としての尊重
- ◆泣きにあたってのなりやすい大人のあり方
- ◆保育のシーンで
- ◆おわりに
すでに登録された方はこちら