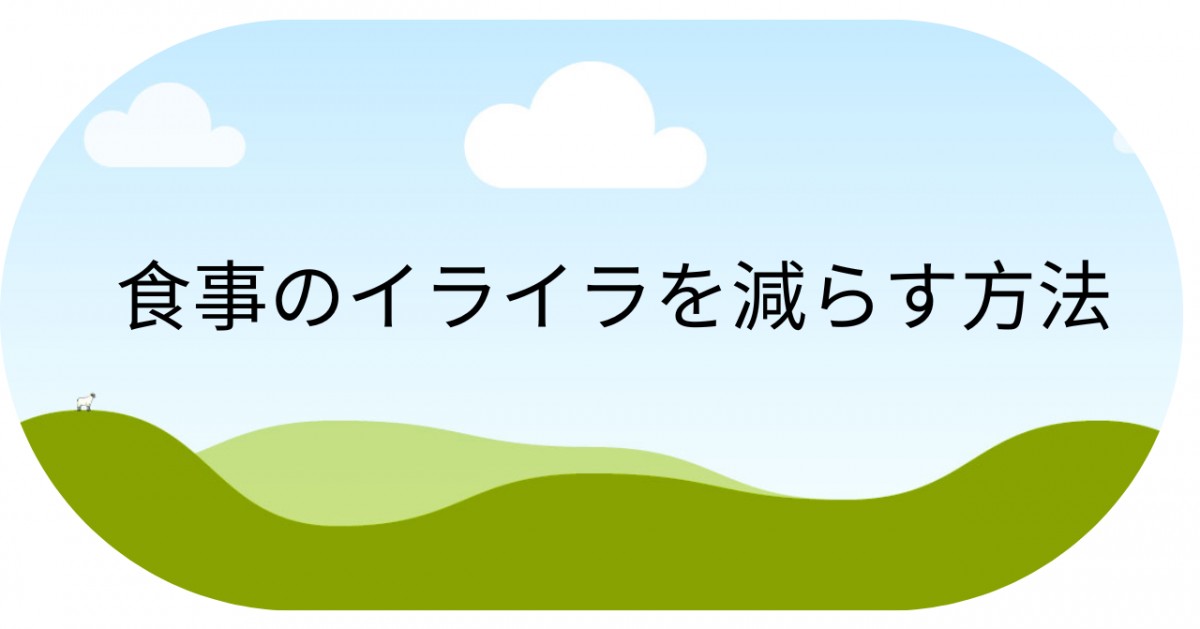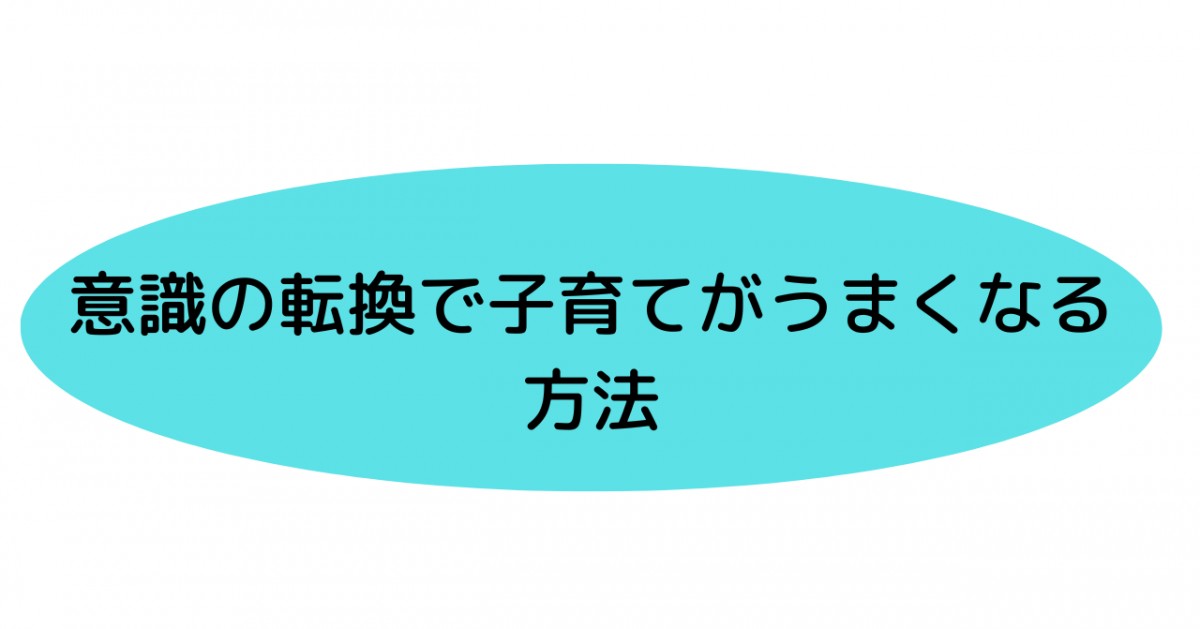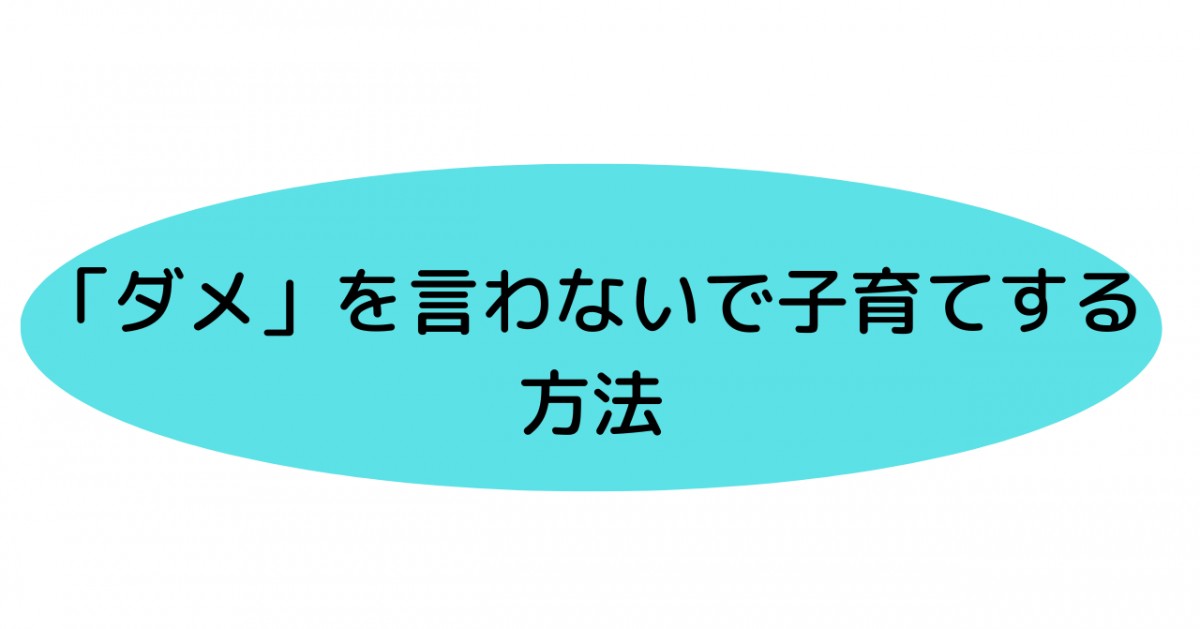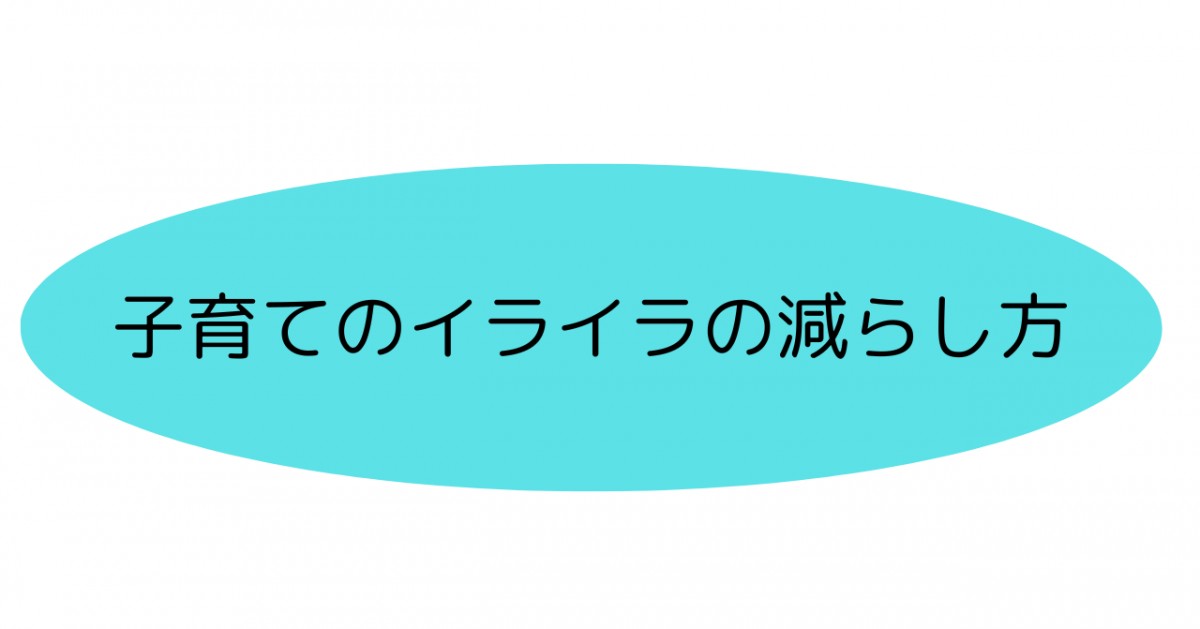家庭が伝えてしまう三つの差別
このメルマガでは乳幼児からの子育てを伝えているわけですが、差別をテーマにするのはオーバーだと思われるでしょうか?
もしそう思う方がいらっしゃったら、むしろそう思う方ほど最後まで読んで欲しいと思います。
おそらく最後まで読まれたあとなんらかの気づきがあることでしょう。
◆家庭が差別の基礎となる現実
差別は多くの人がいけないことだと頭では理解しています。
しかし、精神的にしんどくなるので、できれば考えたりすることも避けたい問題でしょう。
子育ての文脈で差別の話というと、子供がいつのまにか差別にはまってしまい将来的にヘイトクライムをしてしまうかもしれないといった、子育てする人を脅すような内容と思われるかもしれませんが、僕が述べたいのはそれではありません。
それももちろん重要な視点かもしれませんが、差別はもっと身近なところにあり犯罪や加害に手を染めないとしても気をつけなければならないことです。
身近で気がつきにくいゆえに、そちらの方がむしろ基礎的な問題といえるでしょう。
今回とりあげたいのは、家庭内でいつのまにか子供に獲得させてしまう差別心のとりわけ大きいもの三つです。
ひとつは、いわゆる「差別」であるところ。社会的・一般的に差別として取り扱われるもの。
人種差別、障がい者差別、社会的弱者への差別(マイノリティやホームレス・生活保護者等への差別)
ふたつ目は、女性差別。
とりわけ家庭内に密接なのが女性差別です。
また、女性差別は多くの差別の基礎構造、入り口として機能してしまいます。
例えば、人種差別者の多くが同時に女性差別的視点を持っています。
これはたまたまではないでしょう。
人は家庭内で幼少期から無意識・構造的に女性差別に触れていることで、対人関係を上下かつ蔑視的にとらえるようになり、差別に依存するメンタルを形成していってしまいます。
それゆえ、それが入り口となりその他の差別に引き込まれる構造を持っています。
三つ目は、子育て・教育要素と勘違いされて子供にすり込まれ形成される差別心です。
差別とは気づいていてすらそれの対処が難しいものですが、おそらく三番目の子育て要素に内包されている差別心形成はそこに気づくことすら難しく、またそれをしてしまう人ほど気づきにくいものとして存在しています。
大人はそれが差別心の根っこであると気づかないまま、それを用いて子供を育ててしまいます。なので、知っていれば避けられる、知らなければ避けられない問題かもしれません。
この記事は無料で続きを読めます
- ◆差別は知らないことが引き起こす
- ◆差別に対する安定した態度とは
- 1,社会的・一般的に差別として取り扱われるもの
- 2,家庭と女性差別
- ◆非対称性
- ◆呼び方
- 3,他者をさげすむメンタル
- ◆おわりに
すでに登録された方はこちら