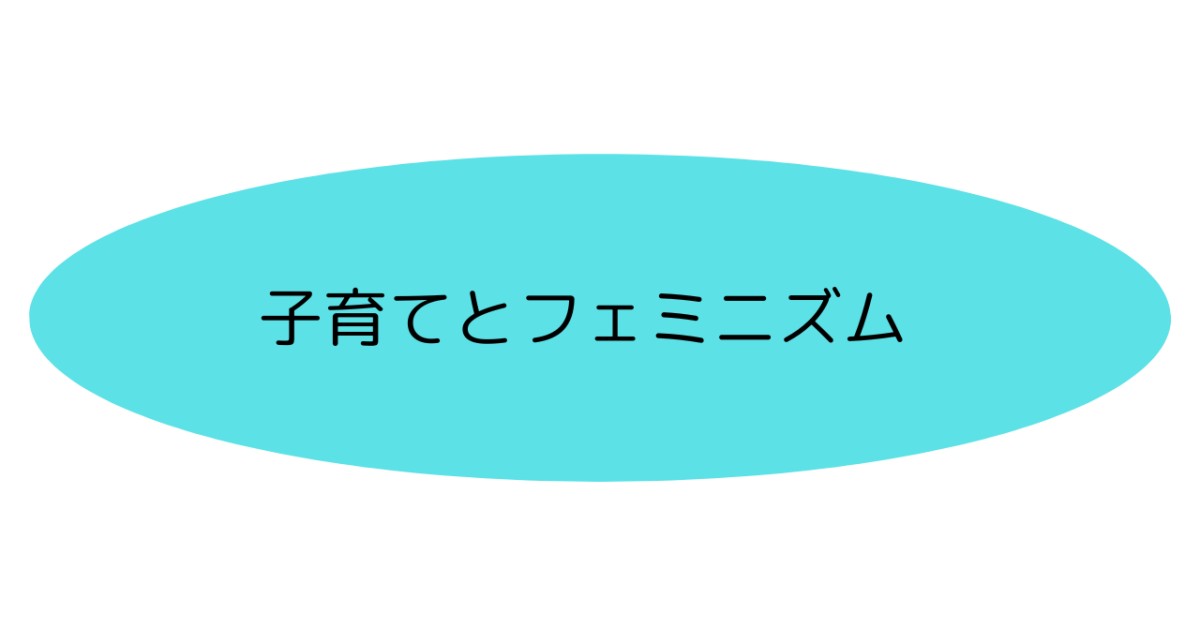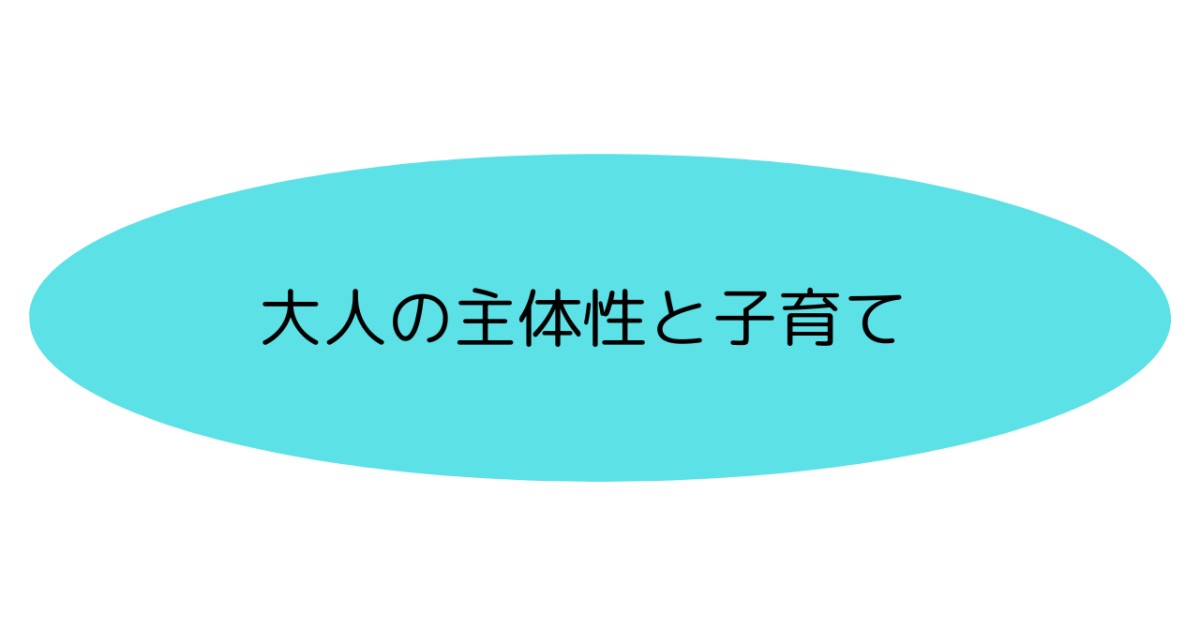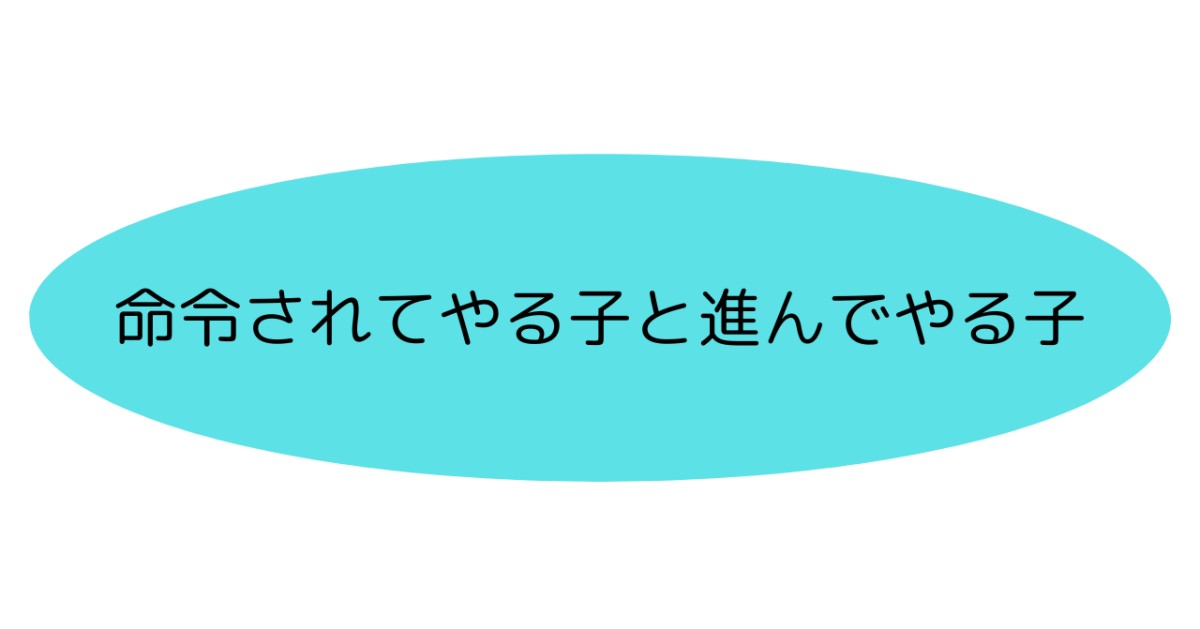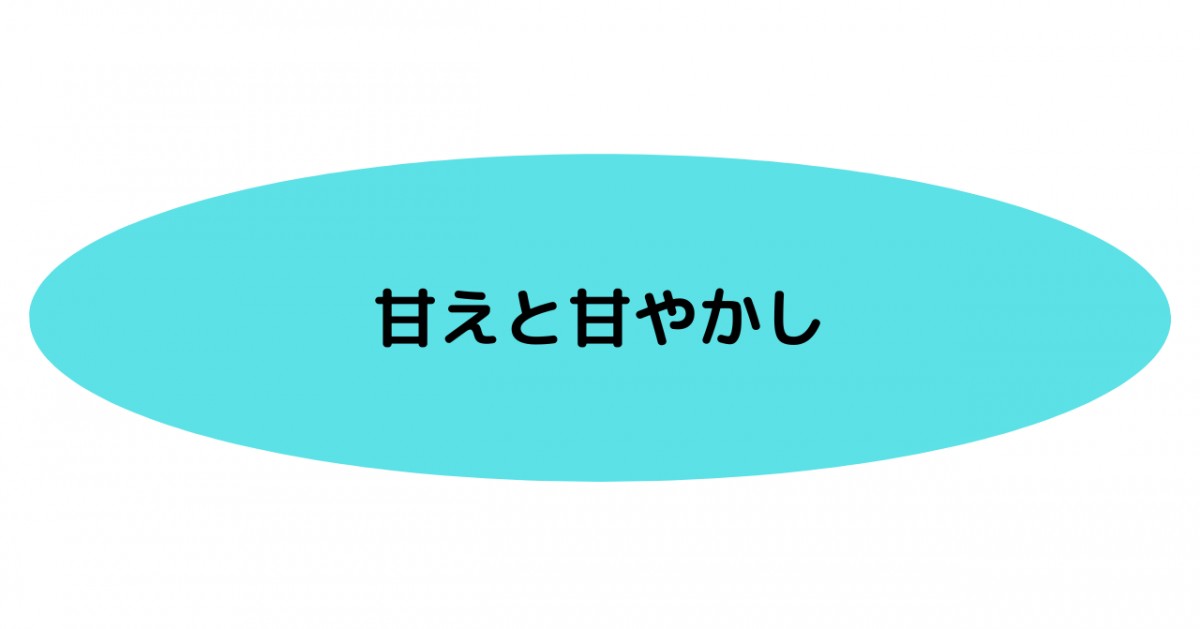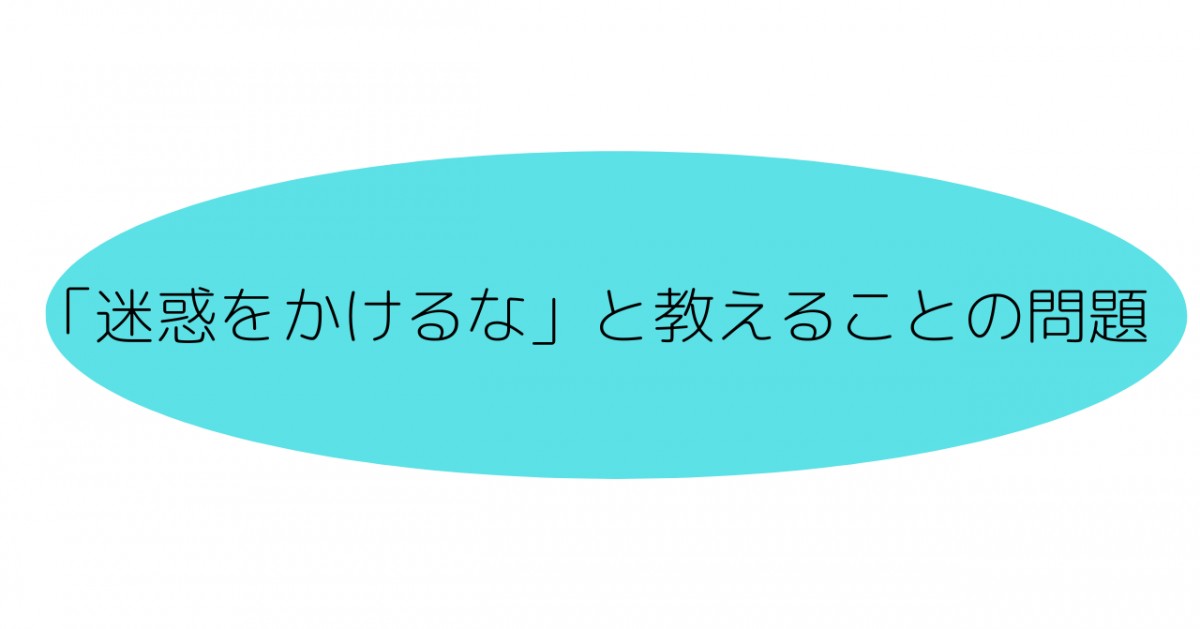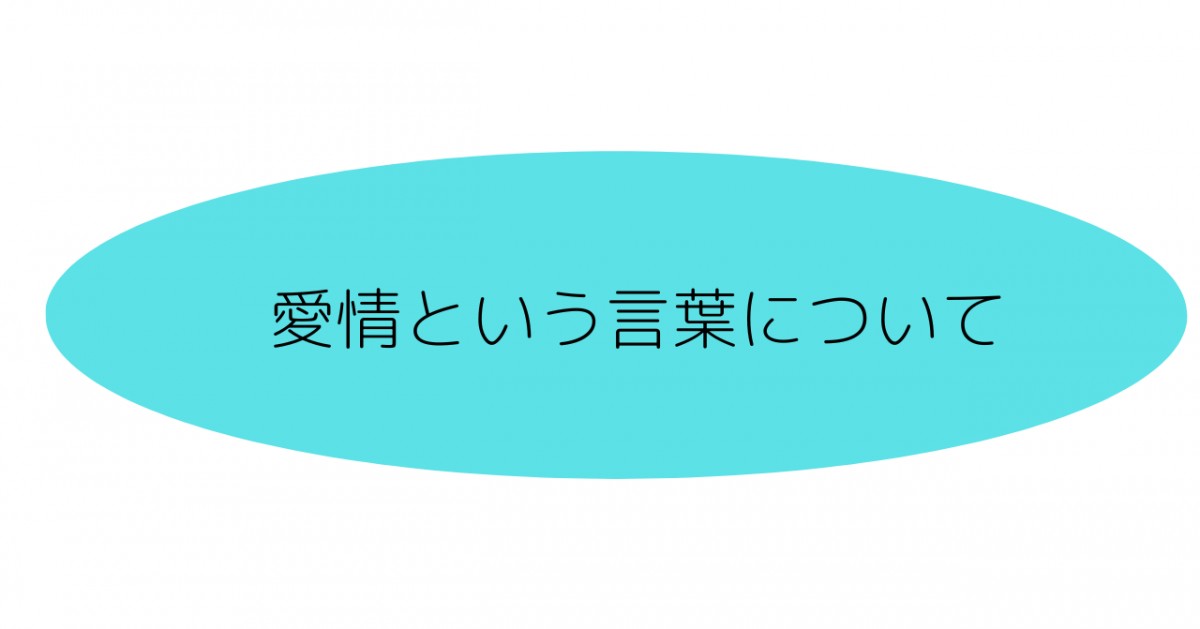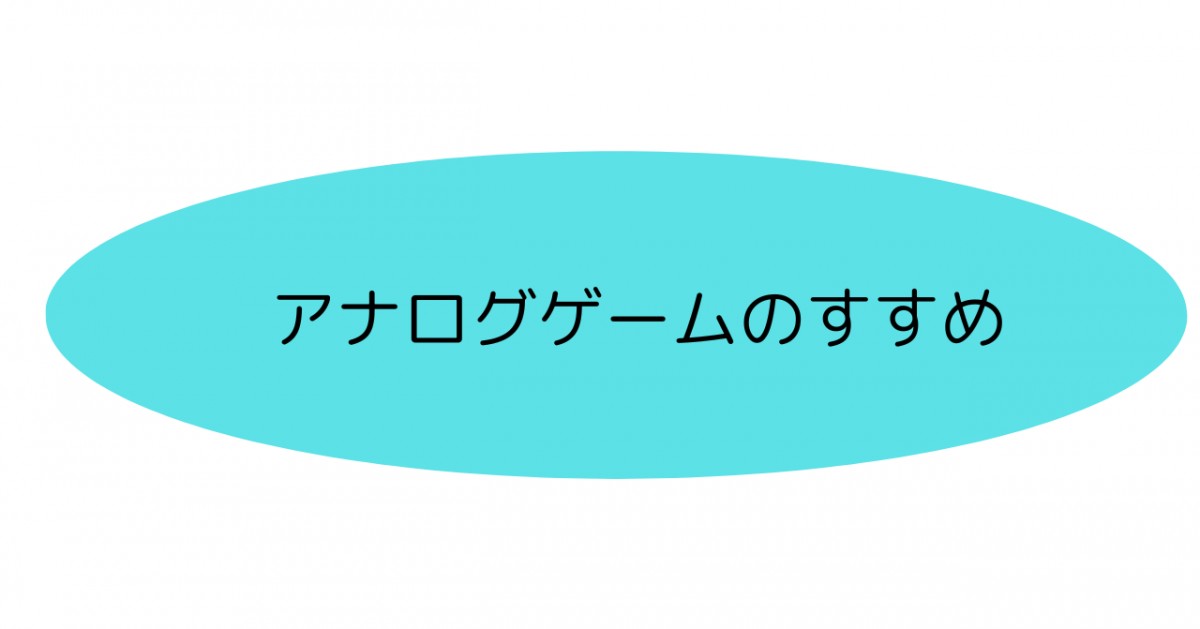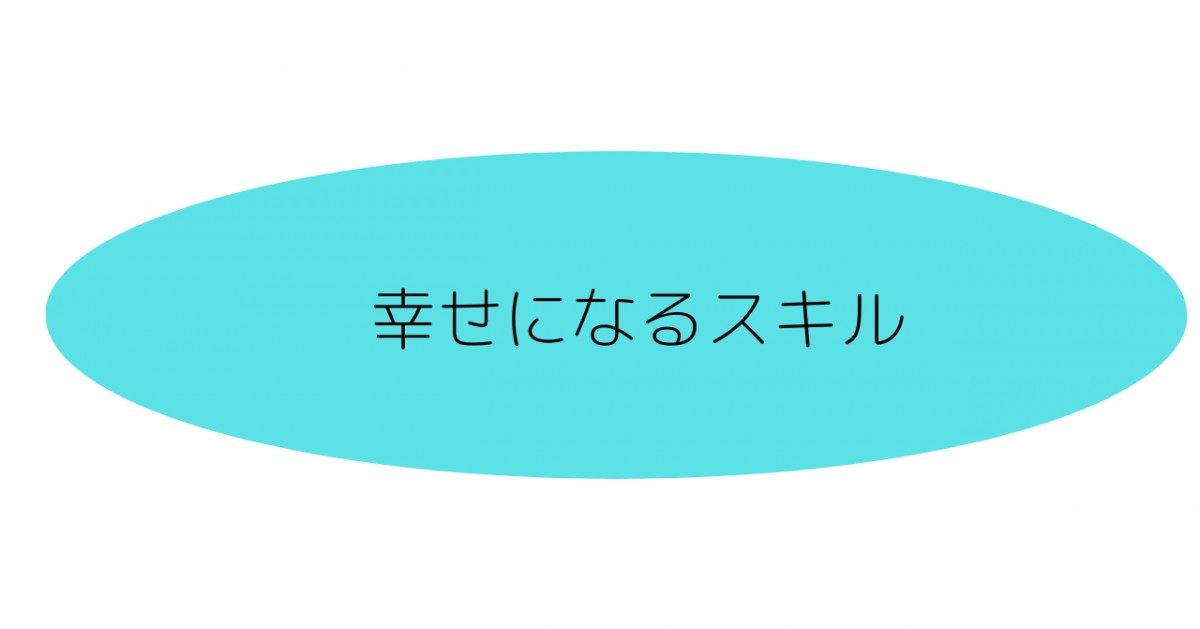いじめをしない子に育てる方法
保育士をしていると子供の意地悪な行為にたくさん触れます。
それ自体は、社会性の獲得途中の課題や、自身の感情のコントロールの課題といった発達上の必要な経験ともいえます。
ただそれが慢性的だったり、それで自分を満たしているといった少し心配なケースもあり、それらはできるだけ解決してあげたいものです。
まして、学校でのいじめが社会問題といえるほどはびこっている現状ではなおさらです。
保育の特徴は、それなりの長期間にわたってその子を観察できることです。
それこそ0歳から6歳まで直接的な園での様子、間接的な家庭や保護者の関わりを知ることができます。そうした知見を並行してたくさん蓄積していけます。
すると、ある程度の因果関係が見えてきます。こう関わるとこうなっていくといった。
もちろん、全てがそのままあてはまるわけではないので個別的な視点も維持しながらそうした知見を有効活用していくのですが。
そうしてみると子供の(発達上の課題以上の)意地悪な行為の多くは、「持たされたもの」としてあることがわかります。
世間ではいじめや意地悪な行為に対して、
注意する、罰する、しつける、ただす、直す
といった感覚や理解を持っている人が多いのを感じます。
僕が少なくとも子供に対して感じるのは、「ケアする」です。
ネガティブなものを持たされて、やむにやまれず意地悪な行為がでているその子の現状をケアして安定的なところに再構築する必要があります。
虐待をしている保護者がいて、その子が乱暴な行為をするといった図式であればある意味ではわかりやすいですが、実際には、保護者がその人なりにまじめに一生懸命子育てした結果、その子がネガティブものをたくさん抱えさせられてその負荷が他者に対して意地悪な行為として現れるといったこともあるものです。
こんなケースがあります。
この記事は無料で続きを読めます
- ◆モラハラ子育てから距離をおく
- ◆加害行為に対してのケア
- ◆モラハラ子育てを防ぐ
- ◆子供の受ける負荷とバランス
すでに登録された方はこちら