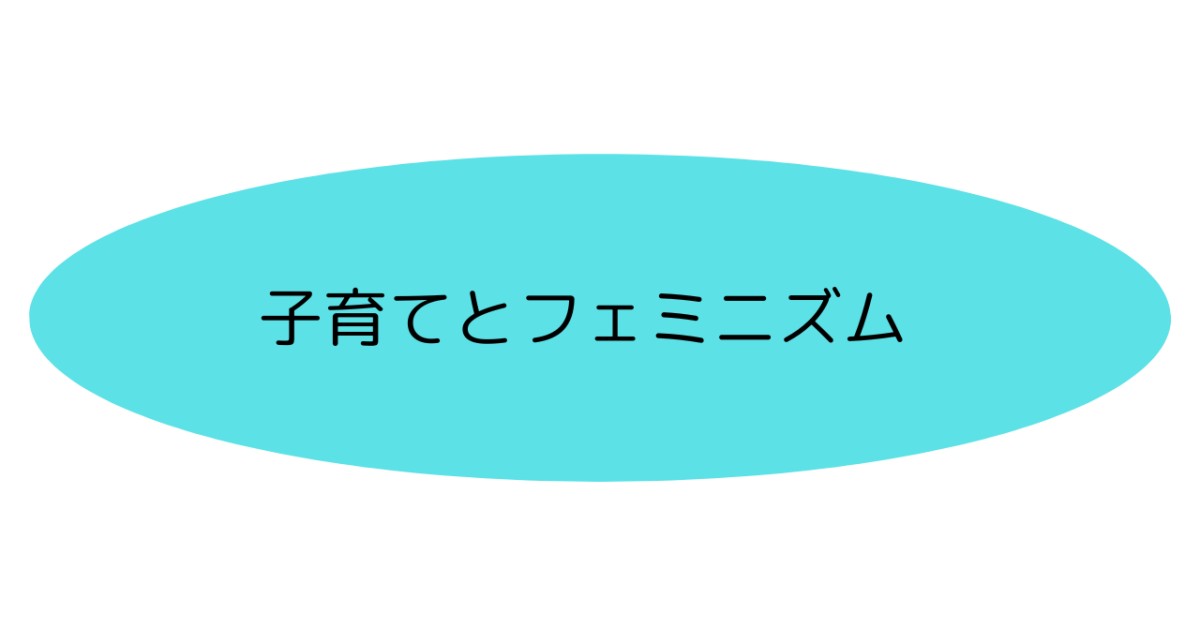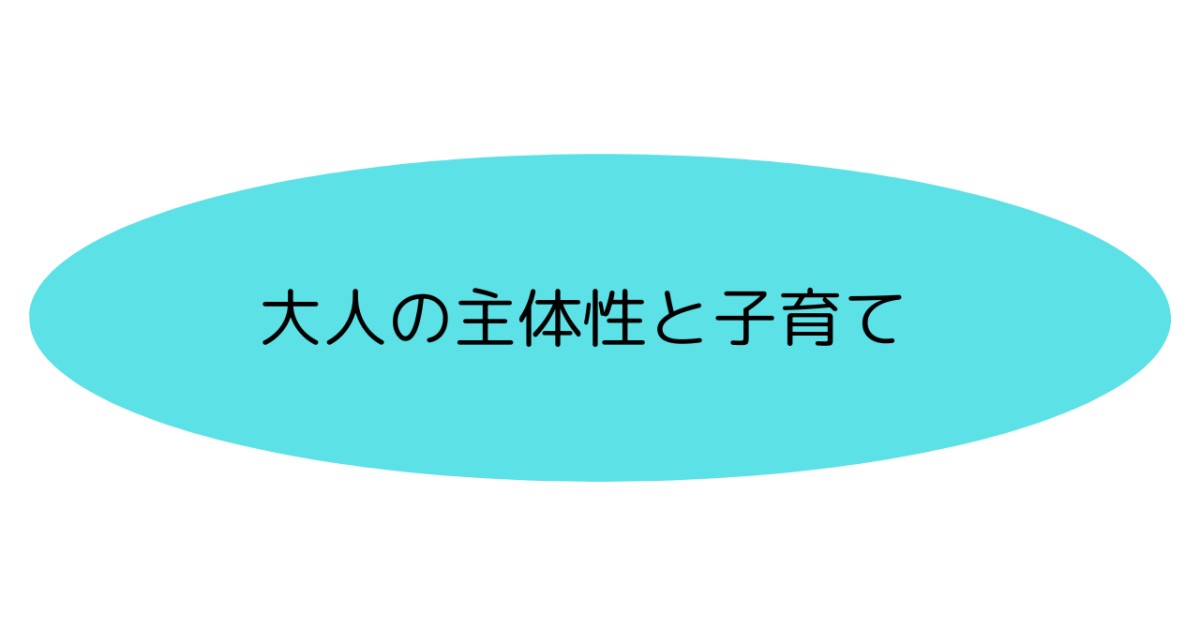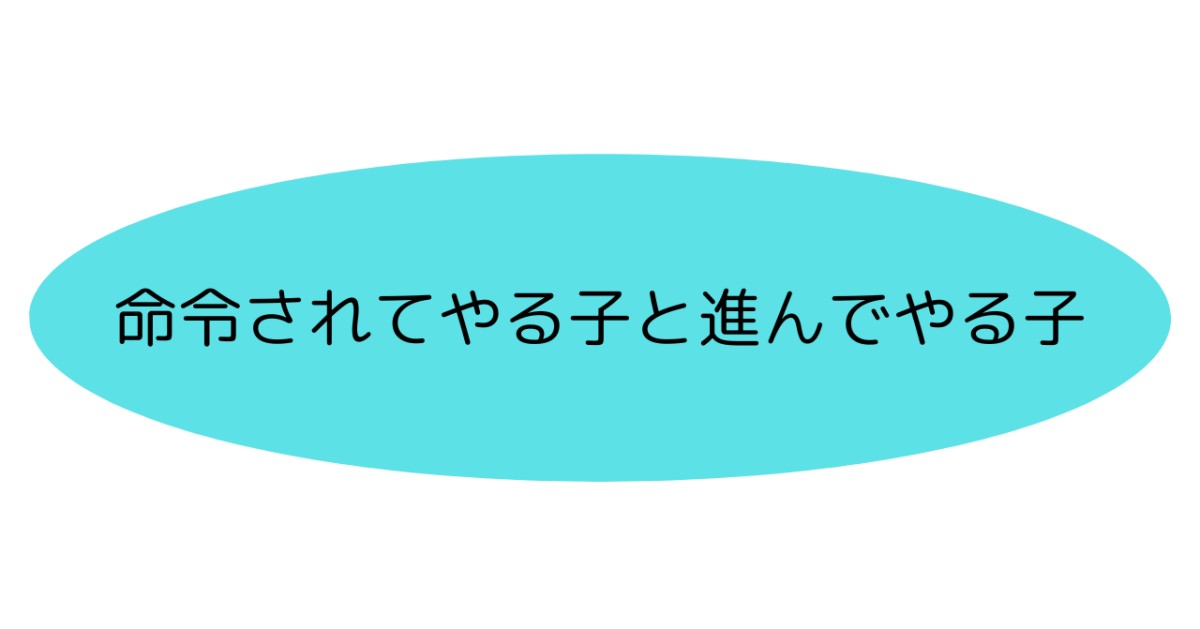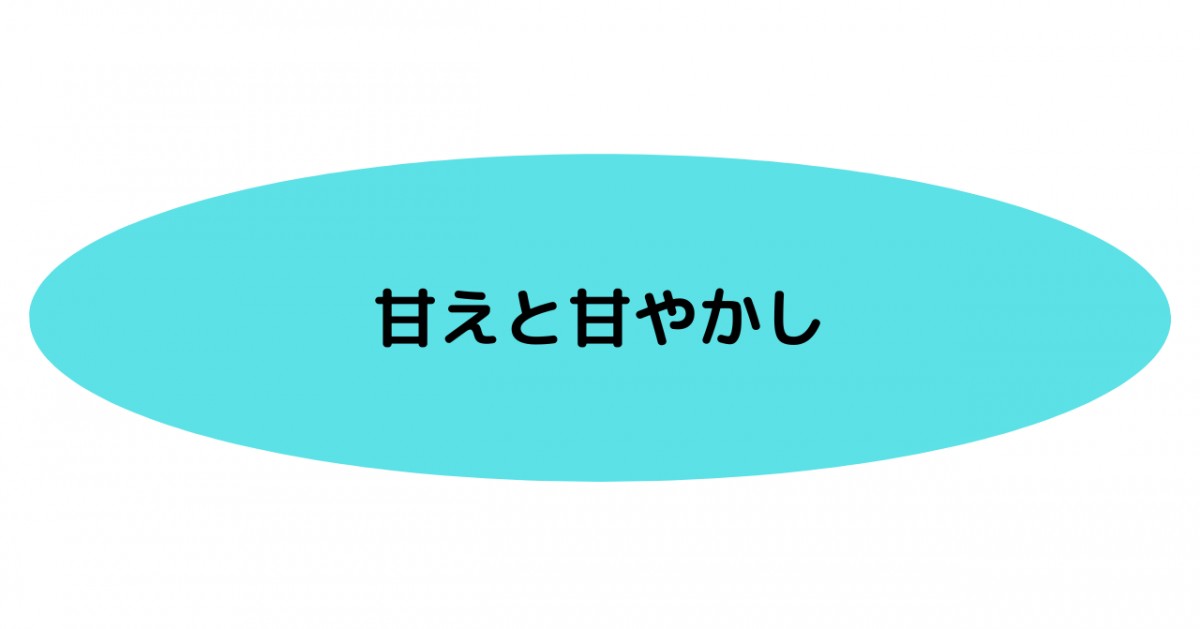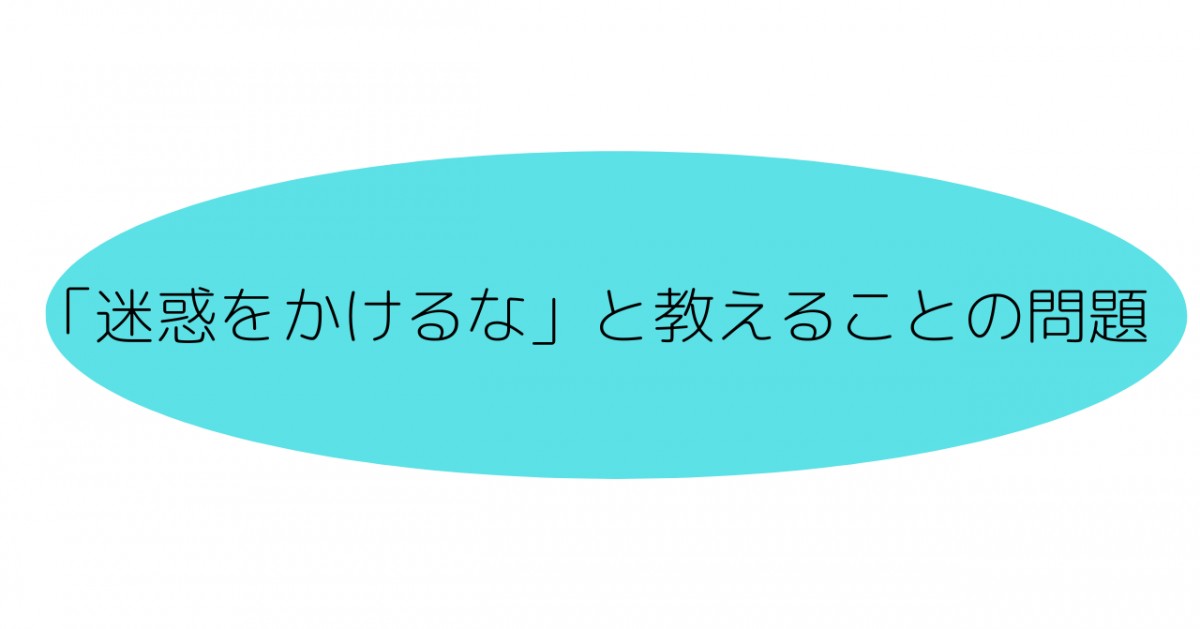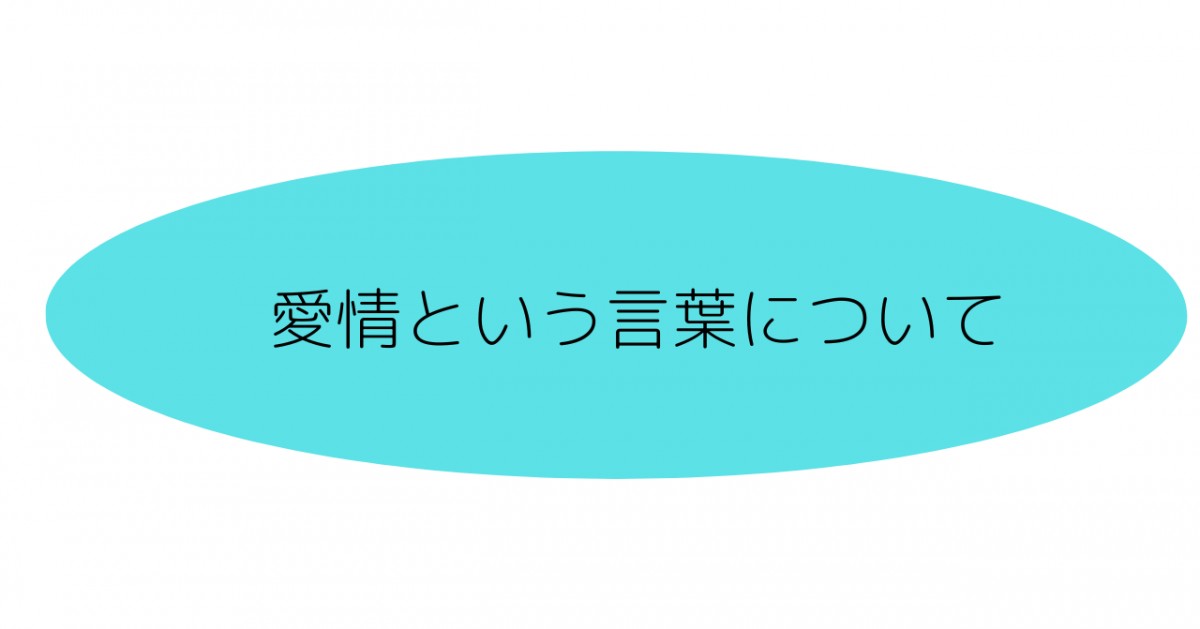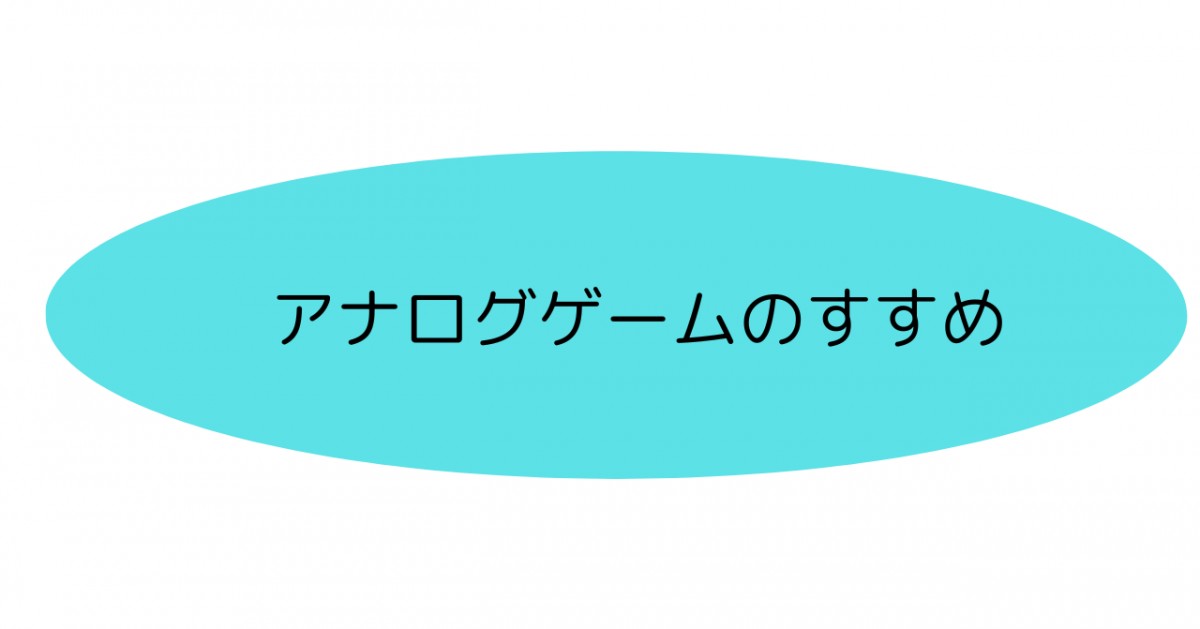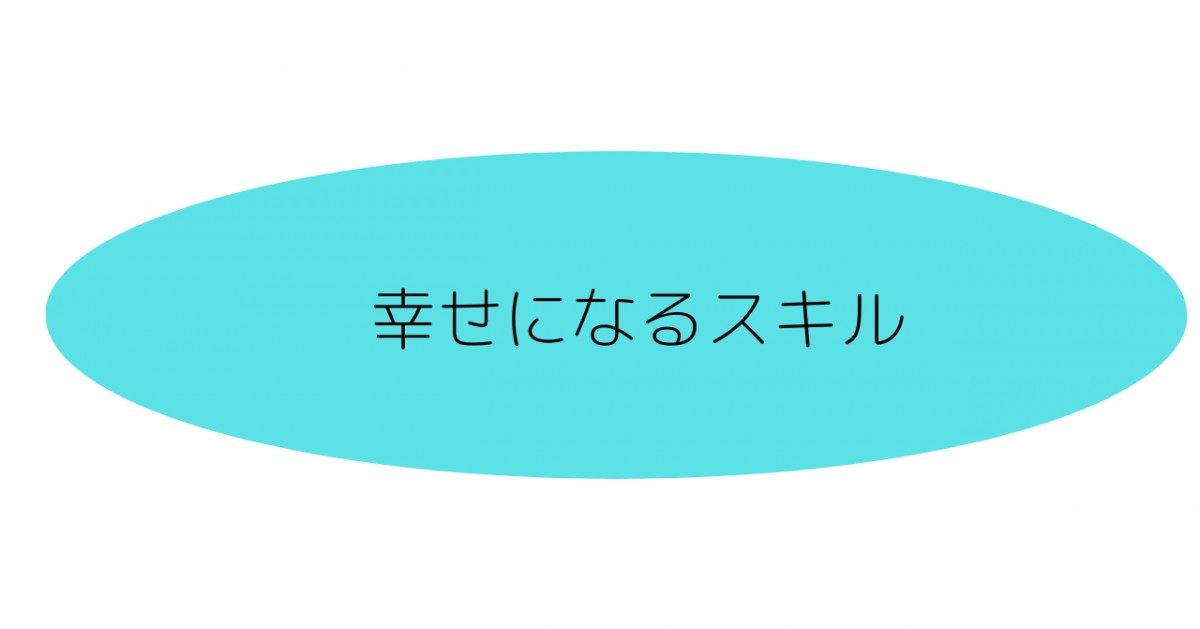力はためてから使う ームリのない子育てのやり方ー
僕が保育士の新人だったときのこと。
幼児クラスの打ち合わせをしていました。
当時僕からすると大ベテランの先輩が、
「子供の力はためてから使うものだと昔先輩に言われたのよ」
となにげなくはなしていました。たしかそのときの議題がお箸の取り組みの時期とその方法だったと記憶しています。
子育てではとくに意識しなければ、子供に求めることが前倒しになりがちです。
3歳でできればいいことを1歳の頃からできるようにしなければと思い、子供にそれを求めはじめるといった具合に。
しかし、少し立ち止まって考えてみるとわかりますが、まだできる基礎的な能力も、やりたいという意欲の芽も出ていない子にそれを求めたとしてもあまり好ましい結果はえられません。
しかし、ある人は不安から、ある人は達成感を求め、ある人はよかれと思い、いまはまだできなくていいことを先取りして求めてしまいます。
発達の早い子の場合、それで結果オーライになってしまうこともあります。
しかし、多くの場合はそうではありません。
大人はできないことに焦りを感じたり、イライラしたり、自分への無力感をつのらせたり。
もしくは、子供がなんとか大人の要求に合わせようと頑張ってくれて、表面上できる姿を見せることがあります。
例えば排泄です。
大人が、「トイレでおしっこしろ」を何度も繰り返し求めてくるので、なんとなく大人の要求に合わせてよくわからないままトイレに座り、よくわからないけどたまたま出た状態を大人が見て大人は満足するといったケースはたくさんあります。
これは表面上はできたように見えて、実際の安定した発達が進んだわけではないので、子供自身の成長から考えるとあまり意味がないことです。
上にでてきたお箸もそうです。
最近は昔ほどではなくなりましたが、かつてはとにかく子供に早くお箸を使わせなければという傾向が強くありました。
特にそれが母親に求められる社会的な空気感がありました。
(いつか解説しますが、↑ここが現代にもつながる子育てを迷走させてきたポイントのひとつです)
なので、本当に早い段階から意味もなく前倒しで求めていました。
◆力はためてから使う
さて、では今日のテーマである
「力はためてから使う」
を考えてみましょう。
もうみなさんわかりますよね。
子育てする人はどうしてもさまざまな理由、特に不安から子供に「○○できる」をたくさん求めがちです。
不安や心配を大人が持ってしまうこと自体は少しも悪いことではありません。
むしろそれで普通です。
しかし、その不安を子供に解決させる方にいってしまうと、子育てそのものが難しくなるし、なにより子供と過ごすことが大人にとっても楽しくなくなってしまいます。
まるで子供そのものが、自分に与えられた宿題のワークブックのように見えてしまいますよね。
※解説「大人の不安を子供に解決させる」
1,大人が子供の成長や行動に不安を持つ
2,大人が子供に干渉してその行為をさせる(それをできるようにとりくませる)
3,子供自身の安定した成長かどうかは未知数だが、大人が不安を解消する
4,この子育てのあり方がループする
現実に起こるケースとしては、
・不登校の子供に学校に行かせるようにしむける行為
・障がいや発達に個性がある子に、過剰に勉強や成長発達の課題を課していくケース
◆成長の秘密
ここで子供の成長の秘密をお伝えしましょう。