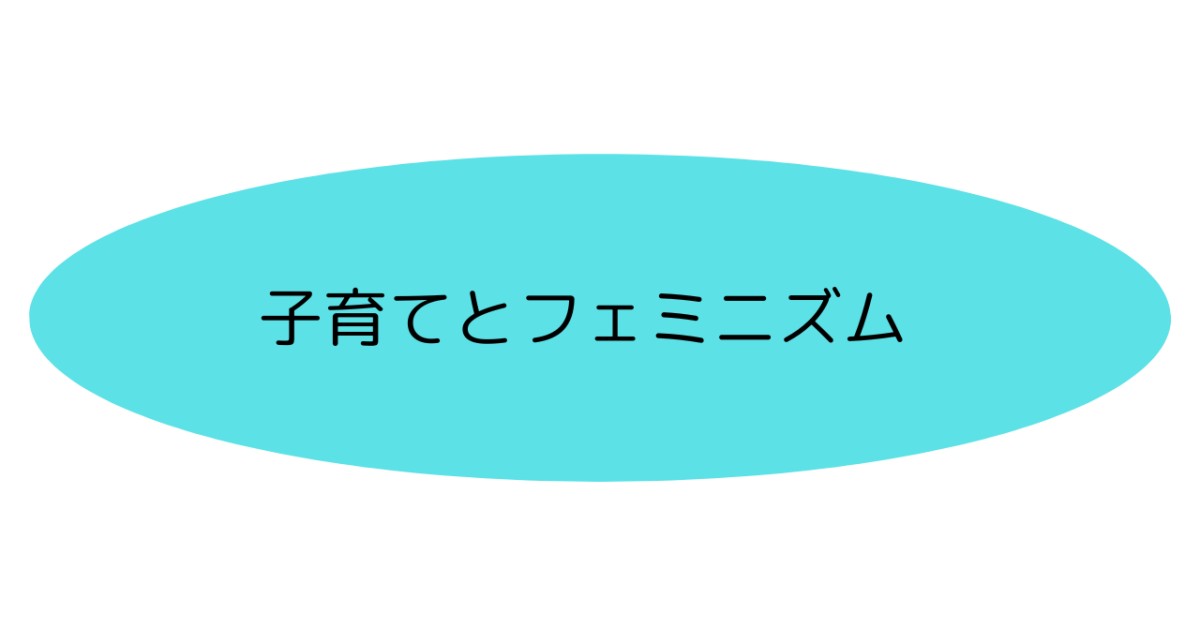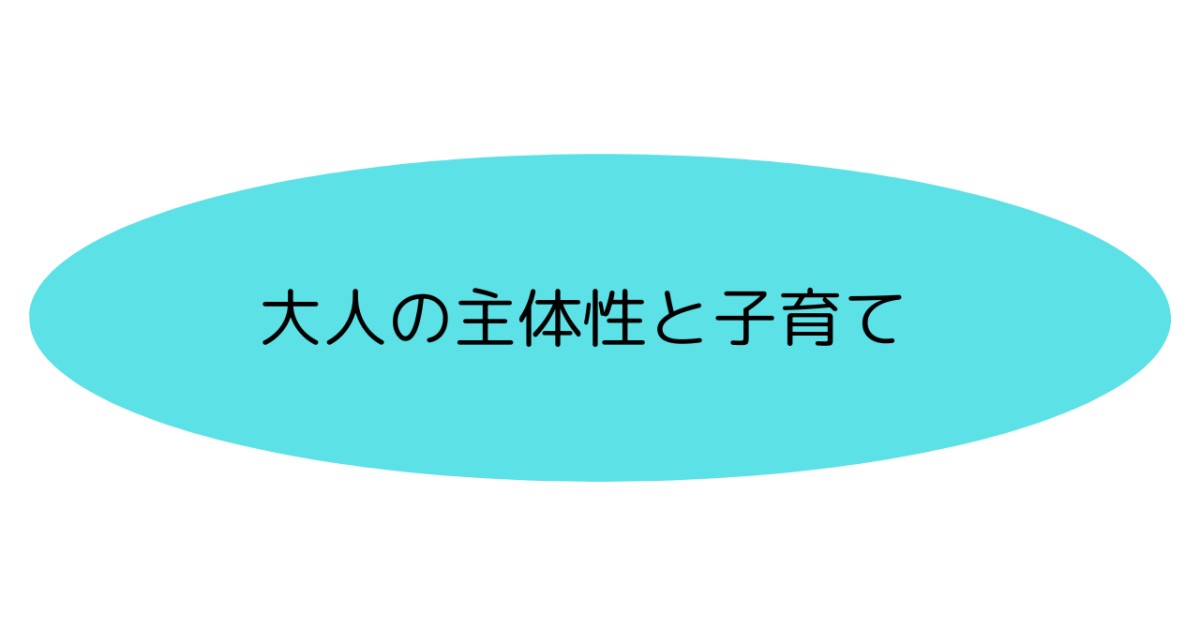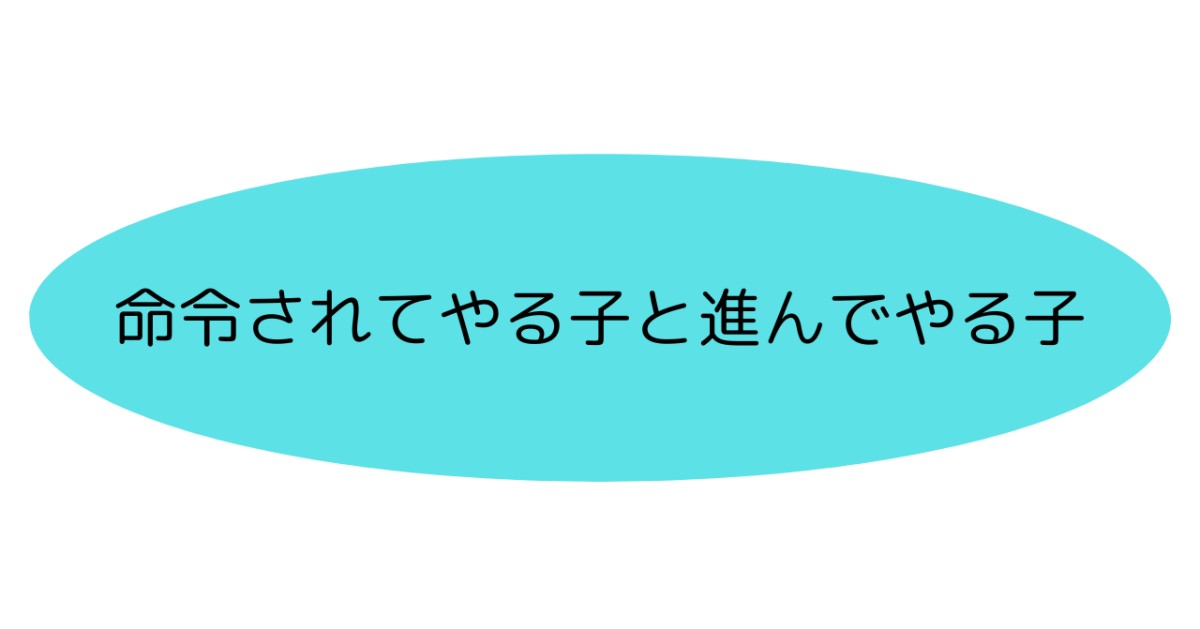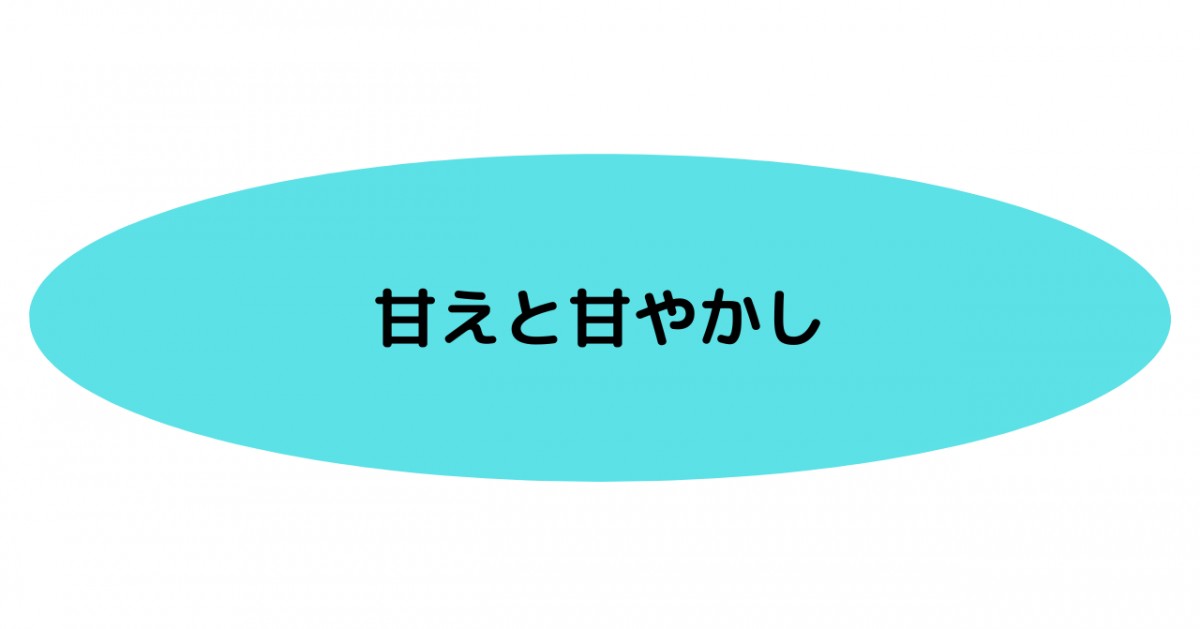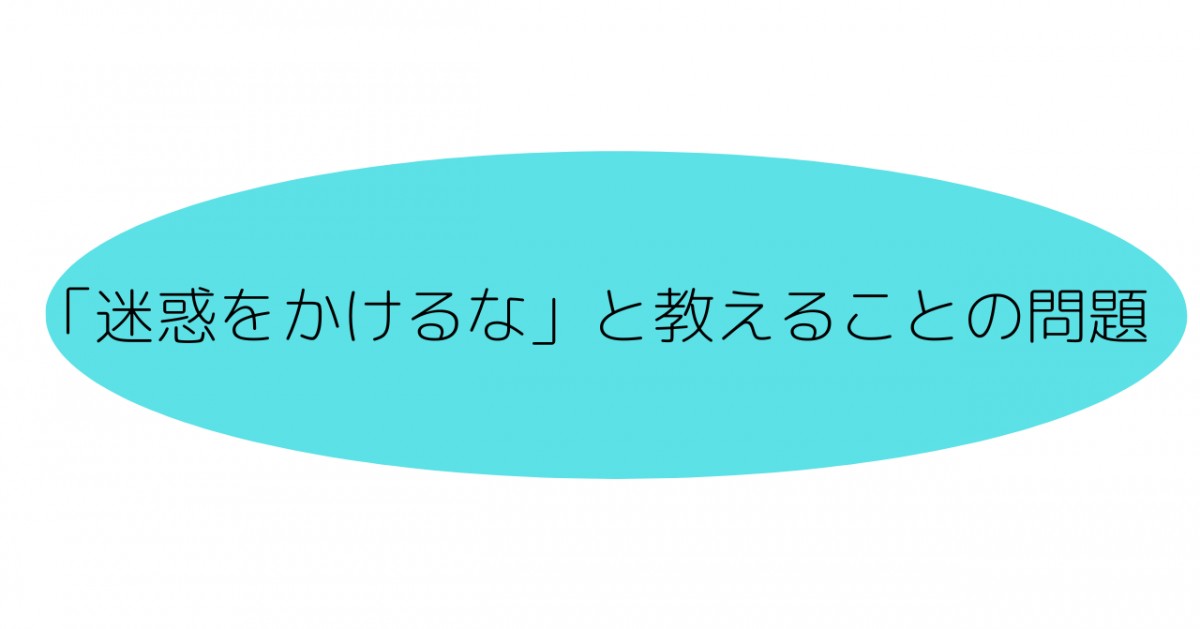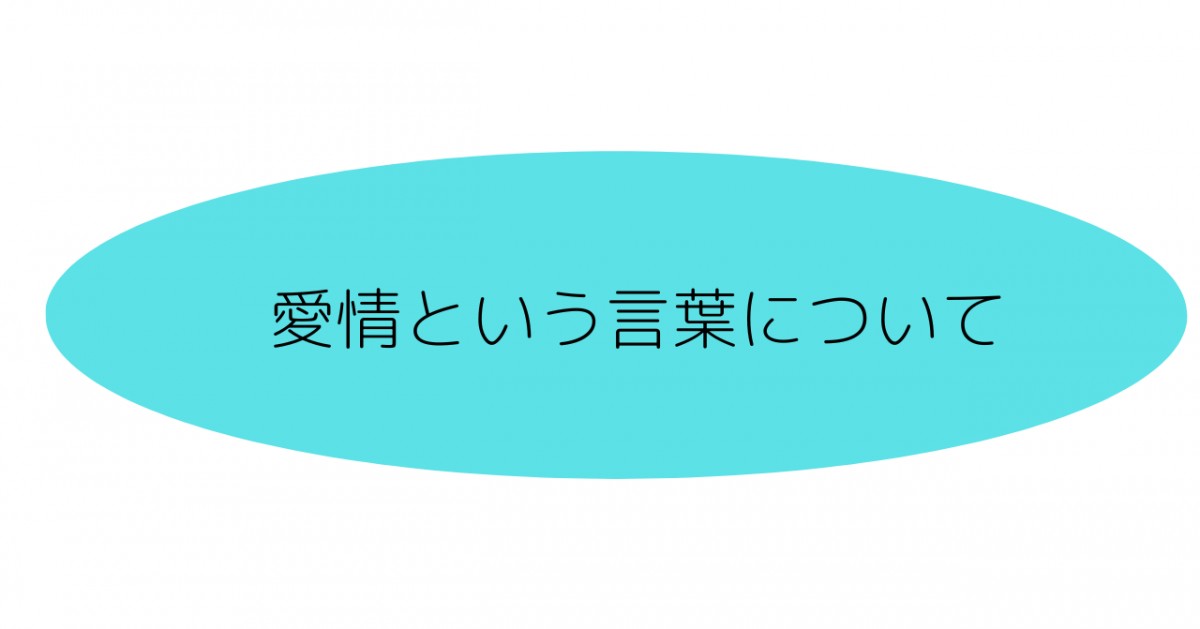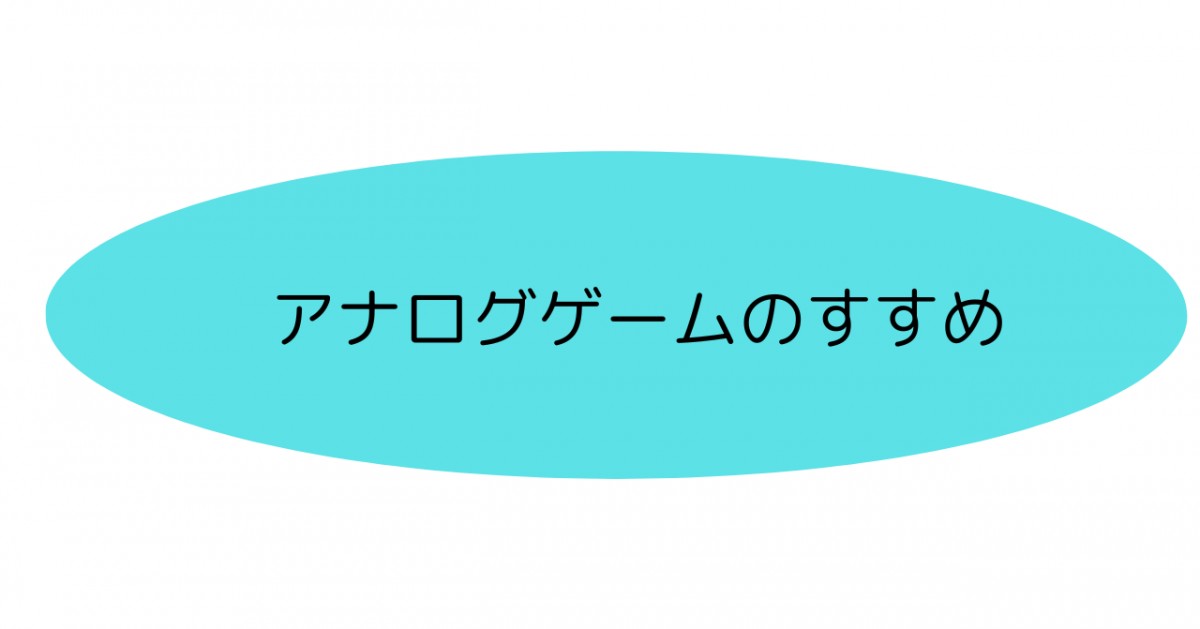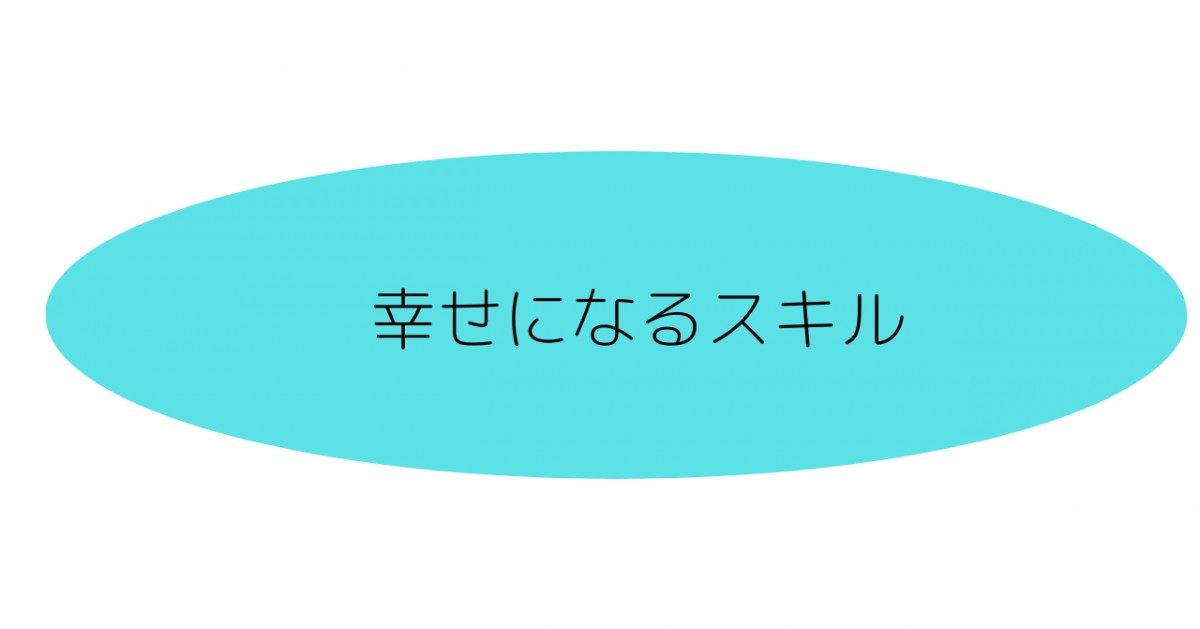子供に関わることの喜びと信頼への責任
子育て真っ最中の人は、子育て全体を俯瞰(ふかん)して子育てそのものを考える余裕なんてないかもしれないので、僕自身が多くの子供達と関わる中で感じて来たことを少し書こうと思います。
僕自身は保育の現場を離れて久しいのですが、いまでもよく保育の現場に戻りたいとも思うのです。
子供、とくに幼少期の子供と関わることのすばらしさには、とても強い信頼を自分に対して抱いてくれることがあげられます。
本来、赤の他人であるはずの保育士にすら、その生活を寄り添って援助していくことでとても強い信頼感を持ってくれます。家族や親に対してであればなおさらでしょう。
なにかうれしいことがあればその信頼する大人を目で探して喜びを共有しようとしたり、怖いことがあれば助けを求めようとしたり。
場合によっては、趣味や嗜好までその信頼する大人の好むものをその子も身につけていくといったこともあります。
例えば、ブドウが好きと公言していれば、いつのまにか子供達もブドウが好きと思うようになっていたり。
家庭の親子関係では、自分の良くない点が子供も似てしまって申し訳ないと思うなんて話もけっこうありますよね。
人間の成長のメカニズムのひとつに、信頼する人の価値観に寄り添うように成長していくという面があります。
これは支配や束縛、干渉的な人格形成ではなく、安定的に成長を援助していくためにとても大切な要素ですね。
例えば、自分自身が食べ物を大切にするという価値観を持っていれば、ことさら教え込まなくてもそうした価値観をいつの間にか共有する方向に育っていけます。(信頼関係が適切に構築されていれば。信頼はあっても他方で支配的関わりが慢性的にある場合などはまた別)
「しつけ」概念のように教え込むものとは違い、これは作為的干渉的ではなく子育ての基礎的な部分にあり、より重要なのですが目に見えない部分なのでなかなかここの大切さというのは認識されづらいようです。
無形の部分だけあり、ウソがつけないところでもあります。
「子供は大人の教えたことではなく、そのときの大人の態度を学ぶ」といった言葉があります。
例えば、「人にいじわるしちゃダメでしょ」と怒鳴って叱ったら、その子が一番学ぶのは、「いじわるしないこと」ではなく、「人に怒鳴っていい」という行為です。
子供は大人に対して強い信頼感を抱いてくれるからこそ、それはとても素晴らしいものである反面、そこに大人としての責任や節度も必要でもあるわけですね。
◆信頼を逆手にとる行為
子供が大人に強い信頼感を持ってくれることは子育ての喜びであり素晴らしいことだと思います。
しかし、現実にはそれを逆手にとってしまう行為もまたありふれています。
その信頼を大人が適切に用いることと、不適切に用いることの境目には、なんの目印もないからです。