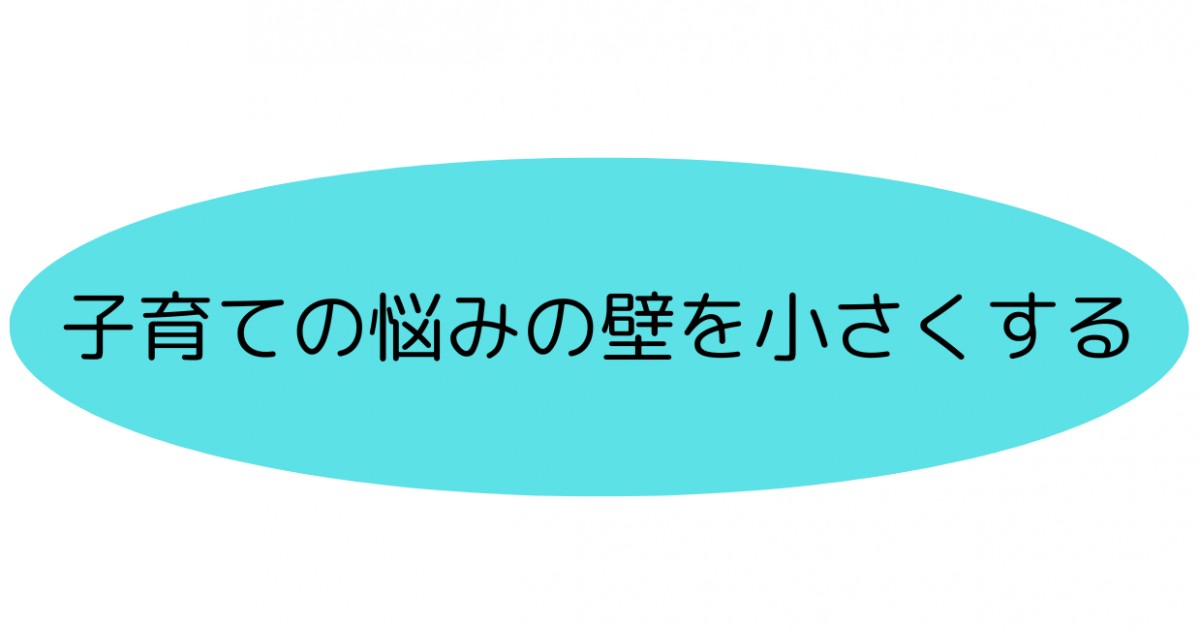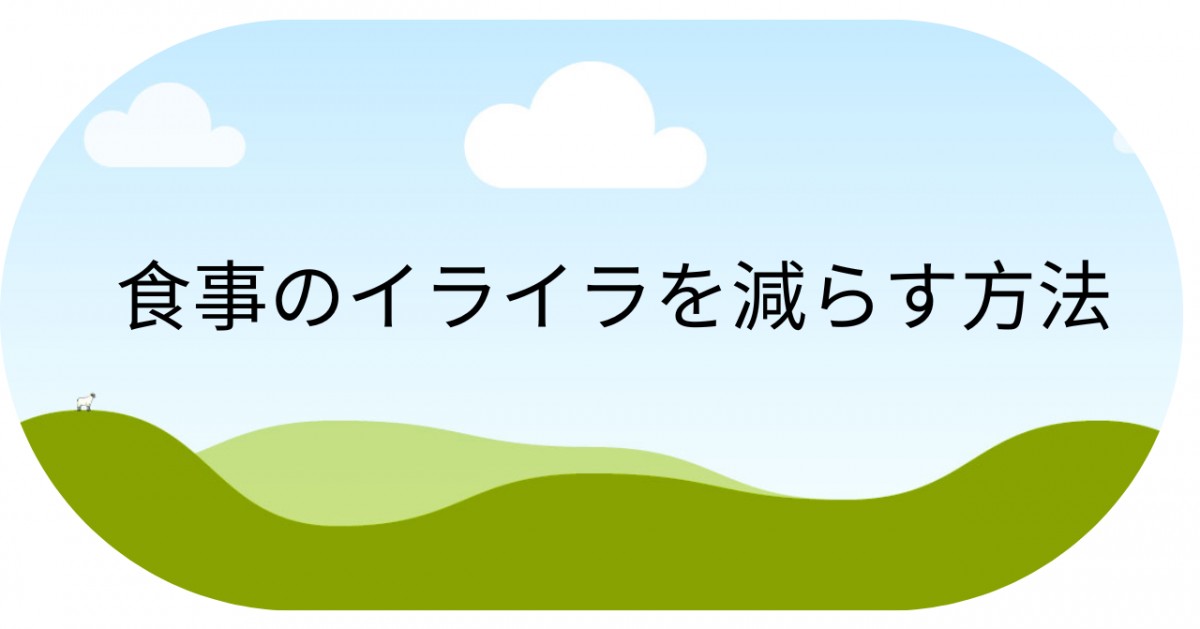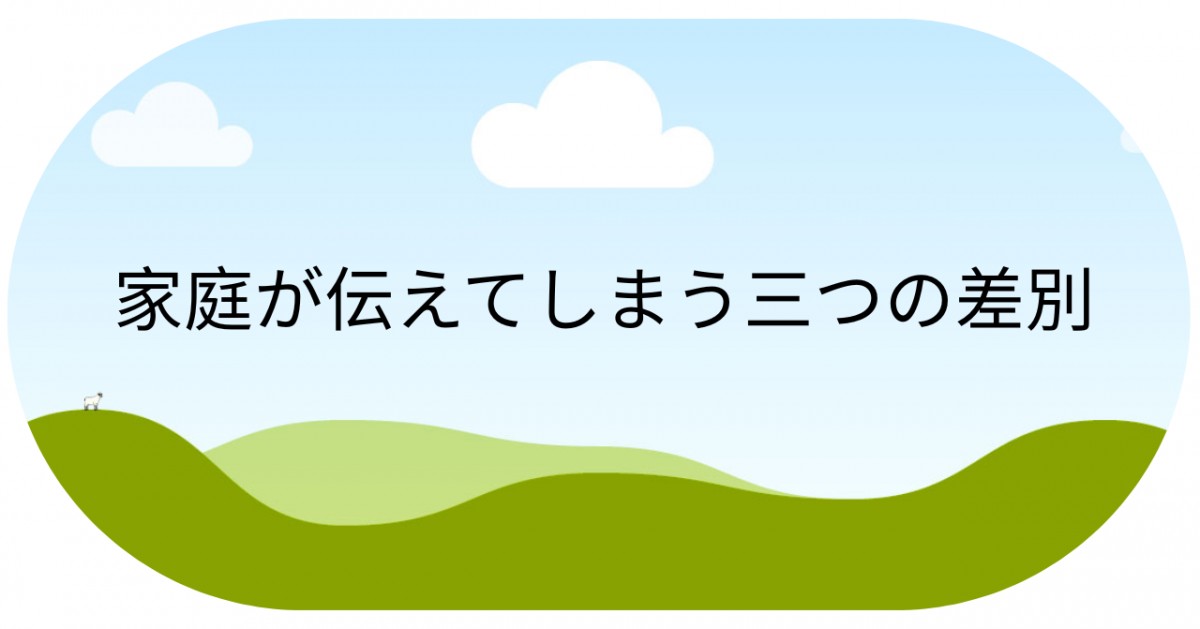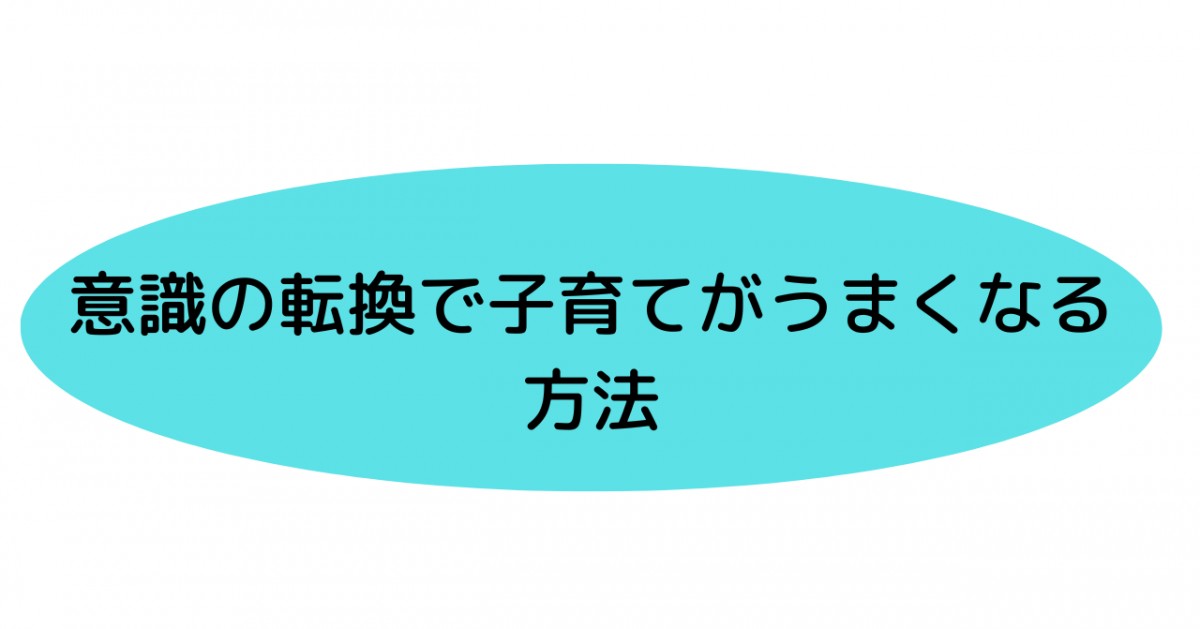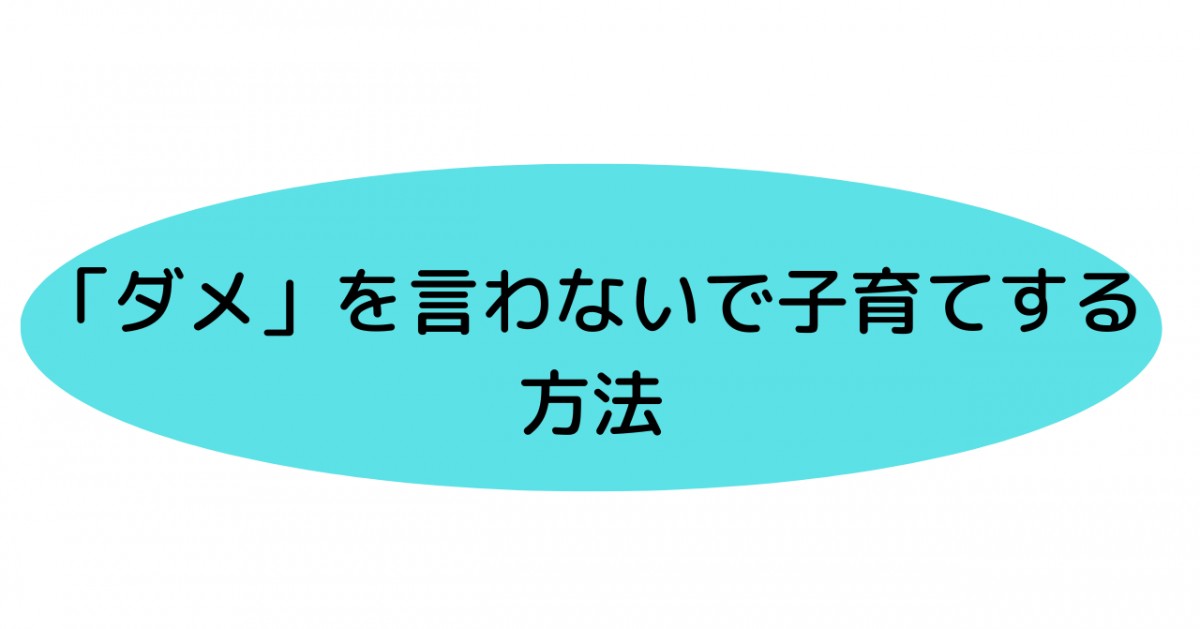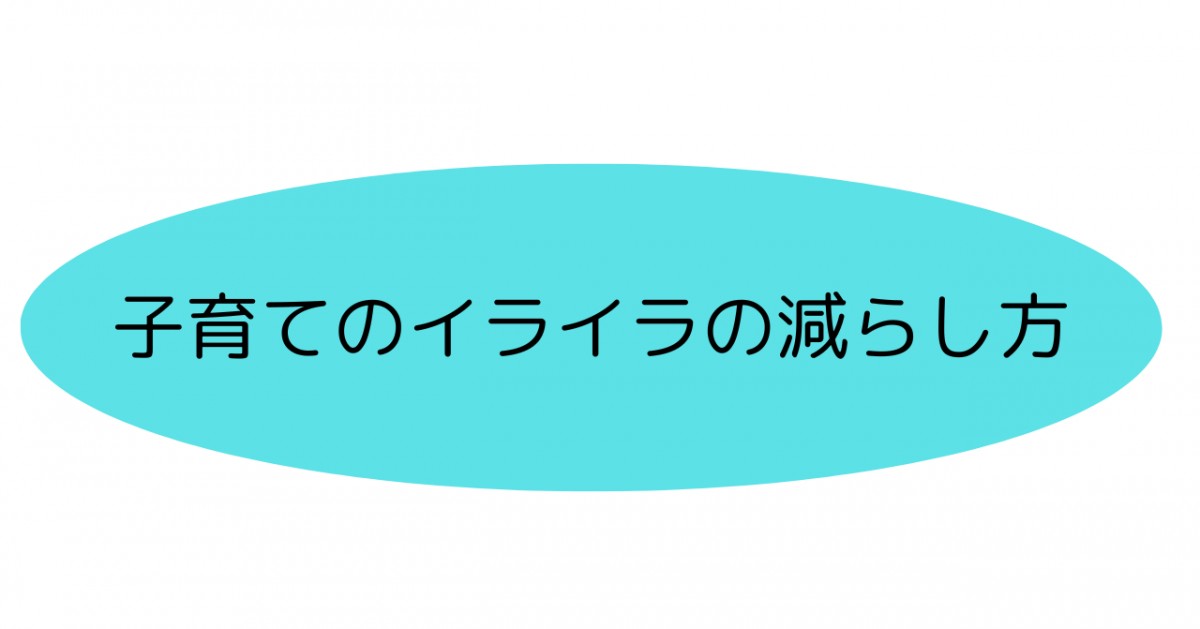モノの貸し借り -「しつけ」がもたらすダブルスタンダード-
モノの貸し借りができるようにと望む人は多いです。
でも、ちょっと気をつけないといけない所があります。次のようなことを子供に教えていませんか?
a 「友達が自分にモノを貸してといってきたら貸してあげなさい」
b 「自分が貸してといったとき、友達が貸してくれなかったら我慢しなさい」
優しさの観点や譲り合いの精神といったところからこれを子供に教えるようになったのかと考えられますが、この二つのことを同時に子供に伝えているとき、実はそこには矛盾があります。
またこれはどちらも自分が損をする形になっています。
このことは情操を育てる上でも必ずしもいいことではありません。「損を我慢すること=優しさ」ではないからです。
(我慢が常態化した人は、優しくなる以上に「自分は割を食っている。他者はずるい」というメンタリティを形成しかねません。このメンタリティの獲得は人格形成やその後の対人関係に大きな影響を与えかねません)
しかし、あまりにも当たり前にこうしたことが一般的に「しつけ」として要求されているので、多くの人は疑問に思うこともないようです。
多くの子がこの大人からの要求をヘンだなとは思っているのですが、大人への信頼ゆえに、なんとなく従いことなきを得てしまいます。
ですが、その子の発達段階や発達上の個性ゆえに、この大人の要求がまったく思う通りにならない子もいます。
こだわりの強い時期やこだわりの強いタイプの子です。
このタイプの子は、ダブルスタンダードをその状況に合わせて臨機応変にあてはめるということが難しいです。